「うつ病や適応障害の診断書はすぐもらえる?」
「うつ病や適応障害で休職するためには診断書は必要?」
「診断書のもらい方や提出の流れが知りたい」
とお悩みの方もいるのではないでしょうか。
うつ病や適応障害で会社を休職する際は診断書の提出が求められるケースがほとんどです。そのため、休職してうつ病や適応障害の治療を始めるためにすぐに診断書を受け取りたいと考える方も多くいます。
この記事では、うつ病や適応障害の診断書がすぐもらえるケースともらえないケースの違いを紹介します。また、うつ病や適応障害の診断書のもらい方についても紹介しています。これを読むと、どのようにすれば診断書がすぐにもらえるのかがイメージできるでしょう。ぜひ最後まで読んでください。
なお、病院でうつ病や適応障害の診断を受けて診断書が発行されるまでには1〜2週間程度の期間が必要となる場合がほとんどです。
そのため、うつ病・適応障害ですぐに休職したい場合は診断書の当日発行に対応したクリニックに相談する必要があります。よりそいメンタルクリニックでは、すぐに休職が必要な方のために診断書の当日発行に対応しているのでご相談ください。
診断書がいますぐ欲しい方へ当院では受診いただいた当日の診断書の発行(※)に対応しております。お困りの方はお気軽にご相談ください。うつ病の診断書をすぐもらいたい場合はお気軽にご相談ください。
本日の受診も受付中です。詳しくは当院ホームページをご確認ください。
→新宿駅前の心療内科・精神科 よりそいメンタルクリニック
※医師が治療上必要と判断した場合のみ、当院書式のみ
うつ病・適応障害とは?

うつ病とは、ストレスやホルモンバランスの乱れにより抑うつ状態や強い気分の落ち込みが見られる精神疾患のことです。
症状の現れ方は患者様によっても異なりますが、様々な意欲の低下や他者とのコミュニケーション障害が生じ症状が悪化すると社会生活を送ることが困難になるため早期の治療が必要となります。
一方で、適応障害とは、職場や学校などで自身が置かれている環境に適応することができずストレスフルな状況が続くことで発症する精神疾患のことです。就職や転職、進学、結婚などさまざまなライフスタイルの変化の際に発症しやすい精神疾患となります。
発症すると気分の落ち込みや不安、出勤拒否、対人トラブルなどが現れます。これらの症状は、個人の日常生活に支障をきたすことが多く早期の対応が必要です。
うつ病・適応障害で休職するためには診断書が必要
うつ病・適応障害で休職を希望する場合、まず医師の診断書が必要です。
診断書は、うつ病・適応障害の症状が業務に支障をきたし休職が必要であることを証明するためのものです。
そのため、会社には自分の症状や今後の判断にも使用されるため休職や退職、継続であっても診断書は必要になることがほとんどとなります。
診断書に記される具体的な内容とは
診断書に記される具体的な内容は以下の通りです。形式が異なっても、基本的な項目は変わりません。
【診断書に記される内容】
|
診断書の用途に合わせて、不必要なところは省略されたり内容が変更されたりします。
うつ病・適応障害の診断書はすぐもらえる?

診断書は、クリニックの体制や患者様の状態に応じて診断書を当日にすぐに発行してもらえることもあります。
ただし、必ず診断書を発行してもらえるかと言えば必ずしもそうではありません。
そのためうつ病や適応障害で診断書をすぐもらえるケースとすぐもらえないケースの違いを理解しておく必要があります。
うつ病や適応障害で診断書をすぐもらえるケース

うつ病や適応障害の診断書は、患者様の症状が重く早急に療養が必要と判断された場合や休職することで症状の回復が見込めると認められた場合はすぐもらうことができます。
ただし、うつ病や適応障害と診断されたとしても診断書の発行に時間が必要なクリニックでは当日診断書を受け取ることはできません。
うつ病や適応障害で診断書をすぐもらいたい場合は、あらかじめ診断書の当日発行に対応しているクリニックであることを確認してからクリニックに訪れるようにしましょう。
また、以下のようなうつ病・適応障害の具体的な症状が見られる場合は、診察の際に詳しく症状を説明することで診断書がすぐにもらえる可能性が高まります。
【うつ病や適応障害の具体的な症状】
|
うつ病や適応障害で診断書をすぐもらえるケースの詳細を確認していきます。
早急に療養して治療が必要
うつ病や適応障害で自殺願望が強い場合は、早急に療養して適切な治療を進めなければなりません。
そのため、直ちに療養が必要と判断された場合n医師はその重要性を理解し迅速に診断書を発行してくれます。
診断書が早期に発行されることで、患者は安心して療養に専念できる環境を整えることが可能になります。
症状が重く一度の診断でうつ病・適応障害と判断できる
うつ病の診断には複数回の診察が必要とされることが多いですが、症状が非常に重い場合は専門医が一度の診断でうつ病・適応障害と判断される場合もあります。
特に、症状が顕著で日常生活に深刻な支障をきたしている場合は、医師が治療の必要性を即座に認識し、すぐに診断書を発行してもらえます。
そのため、診療の際は症状の重さを正確に医師に伝えることが求められます。
クリニックが診断書の即日発行に対応している
クリニックによっては、診断書の即日発行に対応していないことがあります。
その場合、医師からうつ病・適応障害と診断された場合でもその日のうちに診断書を受け取ることができません。
クリニックの方針や混雑状況によっては即日発行が難しい場合もあるため、事前に確認することが重要です。
診断書の発行に関して迅速な対応が可能なクリニックを選ぶことで、患者様はすぐに診断書を受け取ることができます。
うつ病や適応障害の診断書を医師からすぐもらえないケース

うつ病や適応障害の症状が曖昧で診断に至らなかった場合や、症状が軽微で業務に支障をきたすほどではないと判断された場合は診断書がもらえないことがあります。
診察を受けた医師がうつ病や適応障害ではなく他の精神疾患を疑い、更なる検査が必要と判断した場合も同様です。
また、診断書は発行までに1~2週間程度時間がかかることもあるためクリニックによってはうつ病・適応障害と診断されてもすぐに診断書をもらえないケースもあるのです。
うつ病・適応障害で診断書をすぐもらえる人の具体的な症状例

うつ病や適応障害は、非常に深刻な精神的健康の問題であり、早期の診断と治療が求められます。
うつ病や適応障害を発症すると職場や学校、家庭、身体の各場面で症状のサインが見られます。
以下では、それぞれの場面で診断書をすぐにもらえる可能性がある具体的な症状例を確認していきます。
【職場】うつ病・適応障害で診断書がすぐもらえる症状例
うつ病・適応障害を抱える患者に見られる職場での症状の具体例は以下の通りです。
- パワハラがひどくてうつ病・適応障害を発症
- 朝起きると絶望感が強く会社に行きたくない
- 事故に巻き込まれて死んでしまいたいと思う
それぞれのサインの特徴を確認していきます。
パワハラがひどくてうつ病・適応障害を発症
職場でのパワハラが原因で、精神的な苦痛を感じうつ病や適応障害を発症することがあります。
上司からの過度な叱責や同僚からの嫌がらせにより、自尊心が低下し感情の浮き沈みが激しくなるなどの症状が現れます。
パワハラ で心が苦しい場合はうつ病や適応障害の可能性で診断書をすぐにもらえる可能性が高いと言えます。
朝起きると絶望感が強く会社に行きたくない
毎朝、布団から出ることができず、会社に行くことに対して強い拒否感を抱く場合もうつ病や適応障害の兆候と言えるでしょう。
出勤前から心が重くなることで一日のスタートを切ることが難しい場合は、うつ病や適応障害の可能性が考えられます。
事故に巻き込まれて死んでしまいたいと思う
通勤途中などで、交通事故に巻き込まれて死んでしまいたいと考えるようになるのは非常に危険なサインです。
このような思考が現れた場合、すぐにクリニックに訪れて相談をするべきです。
強い自殺願望もうつ病や適応障害のサインとなるためすぐに医師に相談し診断書をもらいましょう。
【学校】うつ病・適応障害で診断書がすぐもらえる症状例
うつ病・適応障害を抱える患者に見られる学校での症状の具体例は以下の通りです。
- いじめによりうつ病・適応障害を発症
- 何もかもが嫌になって将来に希望が持てない
それぞれのサインの特徴を確認していきます。
いじめによりうつ病・適応障害を発症
学校でのいじめから、周囲に対する不信感が募り、心のバランスを崩すことがあります。
自主的に学校を休むようになったり、身体症状としての頭痛や腹痛が頻繁に起こるなどの症状が現れることがあります。
過度ないじめによってどうしようもなく苦しい場合もクリニックに相談して診断を求めるようにしましょう。
何もかもが嫌になって将来に希望が持てない
学校生活での挫折感が大きくなり、将来に対する興味や夢を失ってしまう場合もうつ病や適応障害の可能性があります。
将来に希望を持てず、常に不安な状態が消えないことがあります。
一時的な感情でなく数週間にわたりこのような感情が続く場合はうつ病や適応障害のサインとなります。
【家庭】うつ病・適応障害で診断書がすぐもらえる症状例
うつ病・適応障害を抱える患者に見られる家庭での症状の具体例は以下の通りです。
- 夫婦関係がうまくいかずにストレスが強い
- 転勤による引っ越しで環境にうまく適応できない
- 産後うつにかかり自殺願望が強い
それぞれのサインの特徴を確認していきます。
夫婦関係がうまくいかずにストレスが強い
家庭内でのパートナーとの不和が原因で、日常生活に影響を及ぼすほどのストレスを感じることがあります。
長期的に解決されないストレスが原因となりうつ病や適応障害につながることもあります。
転勤による引っ越しで環境にうまく適応できない
新しい生活環境や社会性に適応できないことは、精神的な負担となります。
知らない土地での孤独感や、慣れない地域社会との関わりに苦しむ場合もうつ病や適応障害のリスクとなります。
新しい環境が心に悪影響を与えている場合は適応障害の可能性が高いと言えます。
産後うつにかかり自殺願望が強い
出産後、育児の疲労や社会サポートの不足から、深刻なうつ状態に陥ることがあります。
特に、自分自身の存在価値に疑問を感じ、絶望感に支配される場合は緊急の対応が求められます。
産後うつも診断書をすぐにもらえる症状であるため早急に医師に相談しましょう。
【身体面】うつ病・適応障害で診断書がすぐもらえる症状例
うつ病・適応障害を抱える患者に見られる身体面での症状の具体例は以下の通りです。
- 1日中抑うつ状態で涙が止まらない
- 死にたい気持ちが強くリストカットなどの自傷行為が見られる
それぞれのサインの特徴を確認していきます。
1日中抑うつ状態で涙が止まらない
無意識に涙が流れてしまう、日中も理由がないのに悲しみが押し寄せる場合もうつ病や適応障害の可能性があります。
日常的なストレスが強く、理由もないのに涙が出る場合も注意が必要です。
クリニックに訪れて相談することでうつ病や適応障害と診断され診断書をすぐもらえる可能性があります。
死にたい気持ちが強くリストカットなどの自傷行為が見られる
自分の存在を否定し、死を望む気持ちが強くなると、自傷行為として現れることがあります。
リストカットなどの自傷行為が止められず心をコントロールできない場合も診断書をすぐに発行してもらえる可能性があります。
退職・休職で診断書を会社に
提出しなければならない
3つの理由

うつ病や適応障害の診断書を会社に提出しなければならない理由は以下の3つです。
【うつ病や適応障害の診断書を会社に提出しなければならない理由】
- 疾患があることを証明するため
- 就業規則で決められているため
- 今後の働き方を決めるうえで現在の病状を把握しておきたいため
以下で、1つずつ詳しく説明します。
理由1.疾患があることを証明するため
うつ病や適応障害の診断書を会社に提出しなければならない理由の1つ目は、疾患があることを証明するためです。
うつ病や適応障害などの精神疾患がある場合、会社側は現在の状況を確認、把握する必要があります。特に、目に見えない症状の多い精神疾患は、どういった状況にあるのかを判断するのは素人では難しいものです。そのため、医師の証明である診断書があると会社にも理解してもらいやすくなります。
理由2.就業規則で決められていることも
うつ病や適応障害の診断書を会社に提出しなければならない理由の2つ目は、就業規則に記載がある場合です。診断書の提出は労働基準法に規定がありません。したがって、会社の就業規則に従って提出の有無が決まることがほとんどでしょう。
会社は、健康状態の把握や仮病での欠勤防止のために、診断書の提出を就業規則で規定していることもあります。また、就業規則に受診する医療機関や医師の指定がある場合もあるため、事前に会社に確認することをおすすめします。
理由3.今後の働き方を決めるうえで現在の病状を把握しておきたいため
うつ病や適応障害の診断書を会社に提出しなければならない理由の3つ目は、今後の働き方を決めるために現在の病状を把握しておきたいためです。
ストレスが原因となるうつ病や適応障害では、環境調整や休職・退職などが必要となるケースもあります。業務内容や、人間関係のストレスを取り除くことで改善が見込まれると医師が判断した場合、診断書にアドバイスが記載されることがあるでしょう。
診断書に書かれている内容は医師からの指示にもなりますので、それに従って会社は環境を調整していく必要があります。
診断書に記される環境調整の例は、以下の通りです。
【診断書に記される環境調整の例】
- 配置転換
- 労働時間の変更
- 残業や夜勤と出張の制限
- 業務量の軽減通院の必要性など
基本的に本人の病状を回復させるための方法が記載されています。産業医や保健師など産業保健スタッフが職場にいれば、間に入る場合もあるでしょう。
職場の人間関係もしくは上司のパワハラなどが原因である場合は、環境を変えることが大切となるため、配置転換などの見解が記されます。
ほかにも長時間勤務が原因であった場合は、労働時間の変更、残業や夜勤と出張の制限などの見解が記されるでしょう。このように、診断書は会社側が環境調整をする参考資料になる場合もあるのです。診断書を医師に依頼する際には、職場環境にストレスを感じているなどの理由を相談するとよいでしょう。
うつ病・適応障害で休職する期間の目安
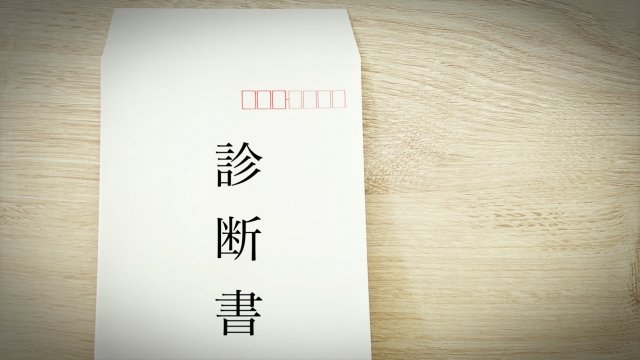
うつ病や適応障害の休職期間は個人差がありますが、一般的には数週間から数ヶ月を要することが多いです。
ただし、病状の重さやストレスの原因が解消されるかどうかによって休職期間は変動します。
医師と相談しながら適切な休職期間を設定し診断書に期間を記入してもらうことが大切です。
会社は診断書に記入された休職期間を目安に休職の手続きを進めてくれます。
うつ病・適応障害で診断書をもらって休職するまでの流れ

うつ病や適応障害によって仕事を続けるのが難しい場合、診断書を取得し休職する手続きを進めることが重要です。うつ病や適応障害で診断書をもらって休職するためには以下の3つのステップを踏んでください。
- 病院を受診して診断書を依頼する
- 会社へ診断書を提出して休職の相談をする
- 休職手続きを行う
それぞれのステップを確認してスムーズに休職手続きをできるようにしましょう。
病院を受診して診断書を依頼する
うつ病や適応障害の兆候を感じたら、クリニックを訪れて専門の医師に相談しましょう。
心療内科や精神科で診察を受けると、適切な診断が下されます。
診断結果として適応障害と判断された場合は、医師に診断書の発行を依頼してください。
診断書は、具体的な症状や休職の必要性が明記されるため、今後の手続きを円滑に進めるための重要な書類です。
会社へ診断書を提出して休職の相談をする
診断書を受け取ったら診断書を会社に提出し、休職の相談を行います。
まず人事担当者や上司に連絡し、診断書を持参して面談を行ってください。
自分の状況や医師の意見を詳細に説明して会社からの理解をえましょう。
休職手続きを行う
休職が会社で認められたら、休職手続きを行ってください。
多くの企業では、休職申請書や休職計画書などの書類提出が求められます。
これらの書類に正確に記入し会社に提出します。また、保険や福祉制度に関する手続きも忘れずに確認しましょう。
うつ病や適応障害の診断書のもらい方

うつ病や適応障害の診断書は以下の順序を経てもらえます。
【うつ病や適応障害の診断書のもらい方】
- 心身の不調を感じたら受診する
- 診断書の発行を依頼する
以下で、1つずつ詳しく説明します。
心身の不調を感じたら受診する
まず、 心身の不調を感じたら医療機関を受診しましょう。うつ病や適応障害は、身体症状が強く出る場合もあるため、診療科がわからないこともあると思いますが、ストレスや不安からの場合は、心療内科や精神科などを受診が好ましいとされております。
うつ病や適応障害などの精神疾患は、初診では診断がつかないケースも珍しくありませんが、まずはクリニックにて相談をしてみることで自分の状態を理解することが大切です。
診断書の発行を依頼する
診断書が必要な場合には、発行を依頼します。その場合には、受付時に事前に伝えておくか、診察時に直接医師に伝えるとよいでしょう。依頼するときには、診断書が必要な理由を伝えるとスムーズになります。
ただし、診断書を依頼したからといって必ずもらえるとは限りませんが、医師がうつ病や適応障害の治療で休養や環境調整が必要であると判断した場合に発行されます。
診断書の有効期限は定まっていませんが、一般的に3カ月です。有効期限を過ぎた場合は、証明書に使えないので、必要な場合は再度発行を依頼しましょう。
診断書の費用の相場
診断書の費用の相場は、2,000~10,000円程度です。全国一律ではなく、医療機関ごとに設定されています。また、診断書の発行は、治療ではないため、健康保険の対象外で、全額自己負担です。
診断書の費用が心配な場合は、事前に問合せておくとよいでしょう。ただし、労働災害で適応障害やうつ病などを発症した場合の診断書費用は労災保険の負担となります。
診断書の有効期間
診断書の有効期限は定まっていませんが、一般的に3カ月です。
有効期限を過ぎた場合は、証明書に使えないので、必要な場合は再度発行を依頼しましょう。
診断書を受け取ったら後の会社へ提出する際のポイント

診断書を受け取った後に会社へ提出する際には、以下のポイントを押さえておくことで、スムーズに手続きを進めることができます。
- 症状の詳細を伝えられるように話したい内容についてあらかじめメモしておく
- 対面が望ましいが難しい場合は電話やメールでも可能
- 会社に詳しい症状や原因、復職の目安など細かく伝える
それぞれ確認しておきましょう。
症状の詳細を伝えられるように話したい内容についてあらかじめメモしておく
会社に診断書を提出する際、自分の症状やその原因について具体的に説明できるように準備することが大切です。
あらかじめ話したい内容をメモしておくと、重要なポイントを漏らさずに伝えることができます。
また、医師の意見や治療計画についても共有すると、会社側も理解しやすくなります。
メモに沿って話すことでスムーズに必要なことを伝えることができます。
対面が望ましいが難しい場合は電話やメールでも可能
診断書の提出や症状の説明は対面で行うことが理想的ですが、難しい場合には電話やメールで行うことも可能です。
電話での連絡時には、診断書の写真やスキャンをメールで送付することで、書類の確認も同時に行えます。
メールの場合は、具体的な症状や医師の意見を文書で詳細に説明するよう心がけましょう。直接伝えにくいからと言って無断欠勤は避けるようにしましょう。
会社に詳しい症状や原因、復職の目安など細かく伝える
休職手続きを進める上で、会社には自分の症状やその原因、復職の見込みについて詳しく伝えることが重要です。
これにより、会社側も適切な対応を取ることができます。また、休職時の連絡方法についても相談をしておきましょう。
休職中に復職時のサポート体制や業務の調整についても事前に話し合っておくことで、復職後の職場復帰が円滑に進む可能性が高まります。
休職後の過ごし方

会社に休職の相談をして休職が認められたら、十分な休息を取り療養に専念することが大切です。ここでは、休職後の具体的な過ごし方を紹介します。
- まずは心身ともに休める
- 徐々に趣味や運動を行いリフレッシュをする
- 休職中に使える各種手続きを行う
それぞれ確認していきます。
まずは心身ともに休める
休職後の初めの段階では、無理をせずに心身ともに休めことが大切です。
たとえば、十分な睡眠を取り、好きな映画や読書を楽しむ、温かいお風呂に入るなど、自分を労わる時間を持ちましょう。
また、ストレスの原因となっている状況や人から距離を置くことも重要です。
無理に外出したり新しいことを始めたりせず、自分のペースで心身を回復させることが一番です。
徐々に趣味や運動を行いリフレッシュをする
休養期間が少しずつ落ち着いてきたら、徐々に趣味や運動を取り入れてみましょう。
趣味に没頭することで心のリフレッシュにつながり、軽い運動を行うことで体のエネルギーも回復していきます。
例えば、散歩をして新鮮な空気を吸ったり、お気に入りの音楽を聴いたりすることもおすすめです。
この時期は自分のペースで無理せず、少しずつ日常生活のリズムを取り戻していくことを目指しましょう。
休職中に使える各種手続きを行う
休職中は、生活の基盤を安定させるために各種手続きを行うことも重要です。
経済的な支援を受けるための手続きや、公的な支援制度の利用に関する情報収集を行いましょう。
これらの手続きを早めに済ませておくことで、安心して休職期間を過ごすことができます。
以下に具体的な手続きの一例を紹介します。
傷病手当金
傷病手当金は、病気やケガで働けなくなった場合に一定の期間、給与の一部を補償してもらえる制度です。
社会保険に加入している方であれば、給付を受けられる可能性があります。
なお、傷病手当金の手続きについては「傷病手当金の書類の書き方は?申請までの流れやよくある疑問を解説」を参考にしてください。
自立支援医療
自立支援医療は、精神疾患や身体障害を持つ方が医療費を軽減するための制度です。
対象となる医療費が通常の3割負担から1割負担に軽減されます。
地域によって手続き方法が異なる場合がありますので役所や支援センターに問い合わせて手続きを行ってください。
うつ病・適応障害の休職後の流れ

うつ病や適応障害で休職した後の復職の流れは、症状の回復状況によっても異なります。
元の職場で復職が可能な場合と復職が難しい場合について紹介します。
復職が可能な場合
復職が可能な場合、まずは医師と相談し、復職のタイミングや働き方について確認しましょう。
その際、職場とのコミュニケーションも重要です。復職前に、上司や同僚と相談し、仕事内容や勤務時間の調整を図ることで、スムーズな復帰が期待できます。
また、復職後は無理をせず、徐々に仕事のペースを取り戻すことが大切です。
定期的に医師のフォローを受けながら、体調管理をしっかりと行いましょう。
復職が不可能な場合
復職が難しい場合は新たな仕事を探すか、しばらく休養を続ける必要があります。
新しい仕事を探す場合は、職業相談所やハローワークを利用して、自分に合った職場を見つけるための支援を受けると良いでしょう。
また、再就職に向けてスキルアップのための研修や講座を受けるのも一つの手です。
休養を続ける場合は、長期的なプランを立て心身の健康を第一に考えて再就職を検討しましょう。
うつ病や適応障害の診断書に関するよくある質問

適応障害の診断書に関するよくある質問をまとめてみました。
- うつ病や適応障害の診断書を会社に提出しなくてもよいケースとは?
- うつ病や適応障害の診断書を医師からもらえないケースとは?
- うつ病や適応障害ではないという診断書を作成してもらえますか?
- 診断書をもらう際のデメリットはありますか?
- 診断書の作成に医療保険は適応されますか?
- うつ病・適応障害で診断書を受け取るとどれくらい休職できますか?
それぞれ詳しく回答していますので、疑問に感じている内容がある場合には、ぜひ参考にしてみてください。
うつ病や適応障害の診断書を会社に提出しなくてもよいケースとは?
心身の不調があっても、うつ病や適応障害の診断がついていない場合は、そもそも診断書の発行が難しい場合もあります。また、就業規則に診断書の提出の取り決めがない場合には、提出しなくてもよい可能性があるでしょう。
この場合の提出は任意なので、提出は本人の意思となります。しかし、会社に現状を把握してもらうためには、診断書を提出した方がよい場合もありますので、慎重に検討しましょう。
うつ病や適応障害の診断書を医師からもらえないケースとは?
うつ病や適応障害の診断書を医師からもらえないケースとは、以下のような場合です。
【うつ病や適応障害の診断書を医師からもらえないケース】
|
うつ病や適応障害の診断がはっきりと確定していない場合は、産業医への診療情報提供だけで診断書の発行はなされません。また、診断書の必要性は診察を担当した医師が判断します。したがって、診察を受けても必ず診断書を作成してもらえるわけではありません。
症状が診られなければ作成してもらえないケースもあります。さらに、不当な理由で請求された場合とは、以下のような場合です。
【診断書が不当な理由で請求される例】
|
第三者からの請求は患者の個人情報を守る目的があり、本人の承諾がある場合にのみ発行が可能です。
うつ病や適応障害ではないという診断書を作成してもらえますか?
うつ病や適応障害ではないという診断書は、作成してもらうことはできません。
医師は診断書発行の必要がある場合に、診断書を作成します。診察して症状が診られなければ、作成できません。
ただ、適応障害が回復した場合には、完治したという診断書の作成は可能です。復職時には、こういった完治を証明する診断書が必要となることもあるかもしれません。
診断書をもらう際のデメリットはありますか?
診断書は休職や福祉制度の手続きで必要となるため、もらうことのデメリットはほとんどありません。
診断書をもらうデメリットをあげるとすれば、発行に費用がかかることです。
記載内容によっても費用が異なりますが、2,000〜10,000円程度必要であることを理解しておきましょう。
診断書の作成に医療保険は適応されますか?
診断書の作成にかかる費用は、基本的には自費診療扱いとなり、医療保険の適用外となることが一般的です。
診断書の発行が保険適用外である理由は、診断書が特定の治療行為ではなく書面による証明書類であるためです。
そのため、診断書を発行するためにかかる費用は、全額自己負担となります。
うつ病・適応障害で診断書を受け取るとどれくらい休職できますか?
うつ病や適応障害で診断書を受け取った場合の休職期間は、医師の診断によりますが通常は1ヶ月から3ヶ月程度が一般的とされています。
しかし、これには個人差があり、症状の重さや就業規則によっても変わることがあることを理解しておきましょう。
診断書には具体的な休養が必要とされる期間が記載されるため、その期間を基に会社や職場の対応が決まることになります。
職場とのコミュニケーションをしっかりと行い、医師と相談しながら、適切な休職期間を設けてください。
うつ病や適応障害での診断書の提出は会社によって異なる

うつ病や適応障害の診断書をすぐもらう条件やうつ病や適応障害の診断書のもらい方について解説してきました。
診断書は、疾患があることの証明となるため、休職の際には提出するようにと就業規則で決められているところがほとんどです。
また、就業規則では決められていなくても提出を求められるケースもあります。その場合は任意となりますが、会社に病状を把握してもらうためにも提出しておいた方がよいでしょう。
なお、クリニックによっては診断書の発行には1〜2週間程度の期間がかかることがあります。よりそいメンタルクリニックでは、診断書の当日発行に対応しているためすぐに診断書を受け取り休職手続きを進めたい方は当院までご相談ください。
診断書がいますぐ欲しい方へ当院では受診いただいた当日の診断書の発行(※)に対応しております。お困りの方はお気軽にご相談ください。うつ病の診断書をすぐもらいたい場合はお気軽にご相談ください。
本日の受診も受付中です。詳しくは当院ホームページをご確認ください。
→新宿駅前の心療内科・精神科 よりそいメンタルクリニック
※医師が治療上必要と判断した場合のみ、当院書式のみ
参考サイト・文献
・就業規則を作成しましょう|厚生労働省
・モデル就業規則について|厚生労働省
・医師法|厚生労働省
・メンタルヘルス 不調をかかえた労働者に対する治療と就労の両立支援マニュアル|独立行政法人 労働者健康安全機構



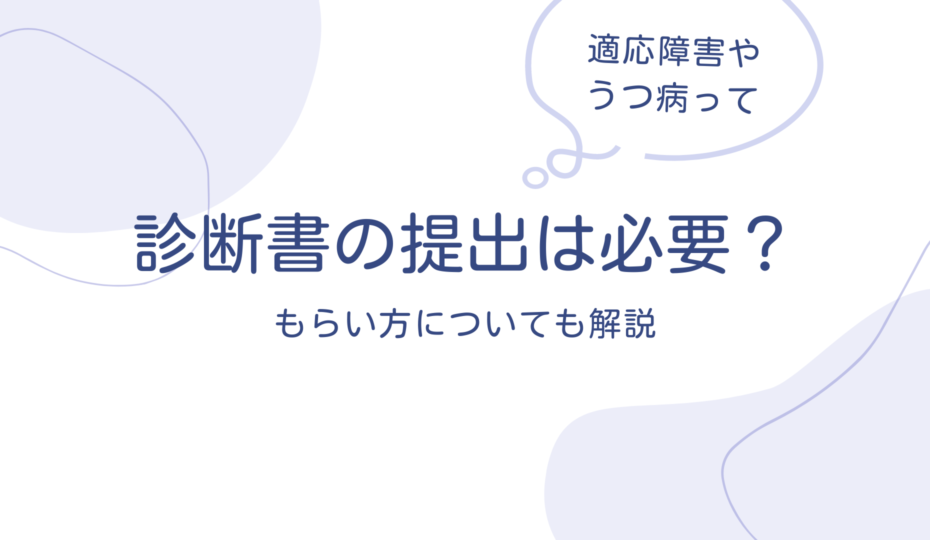
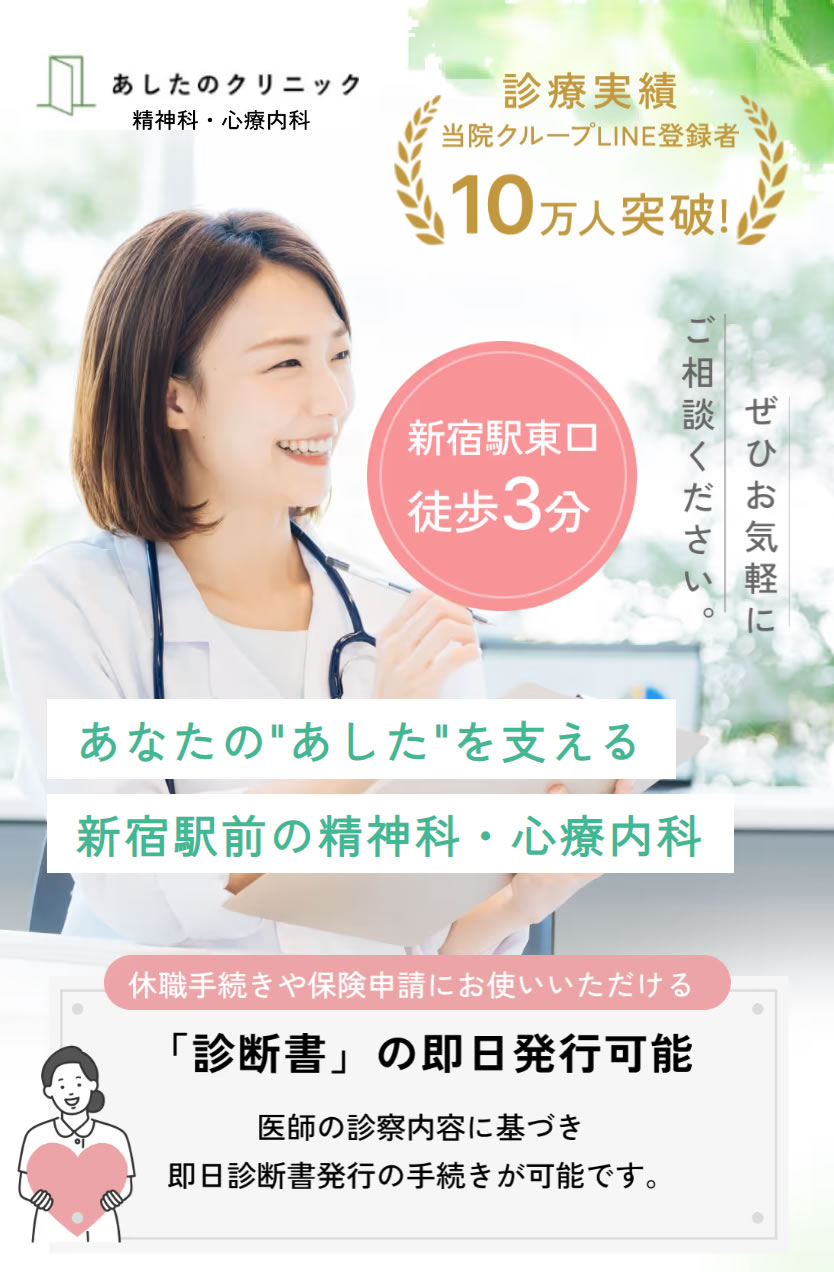

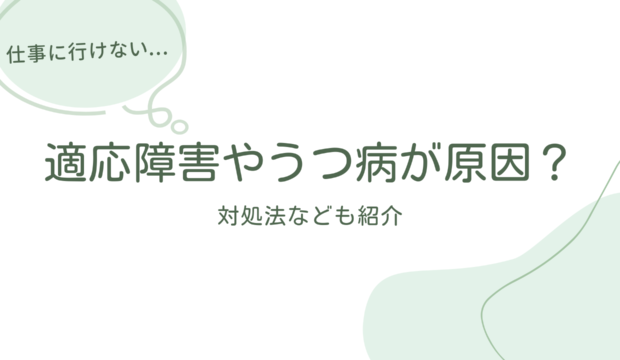
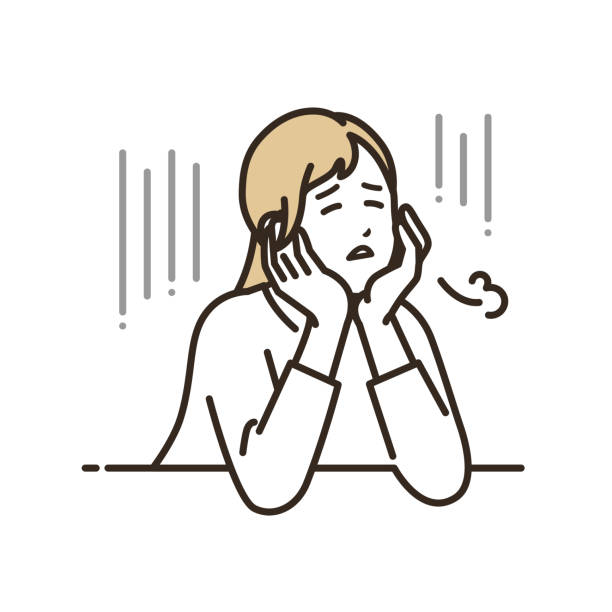





コメント