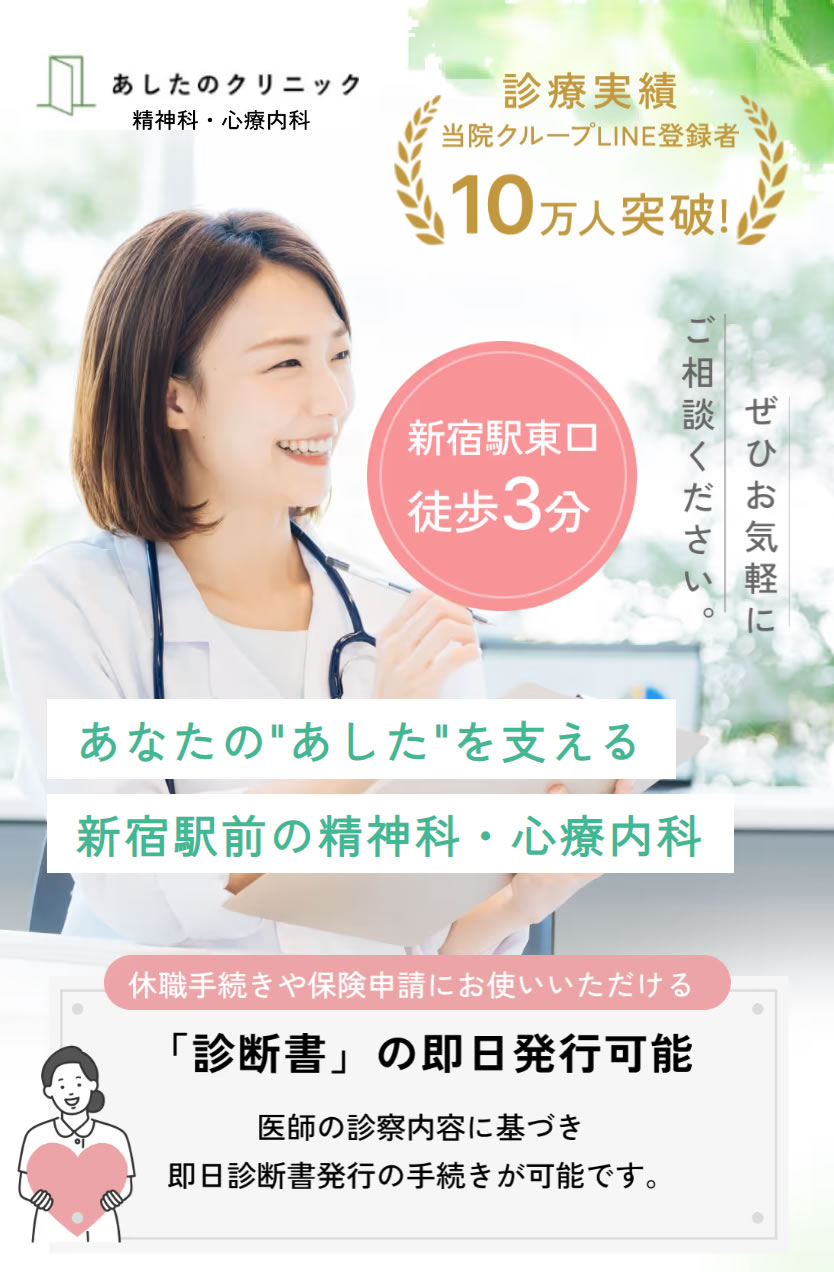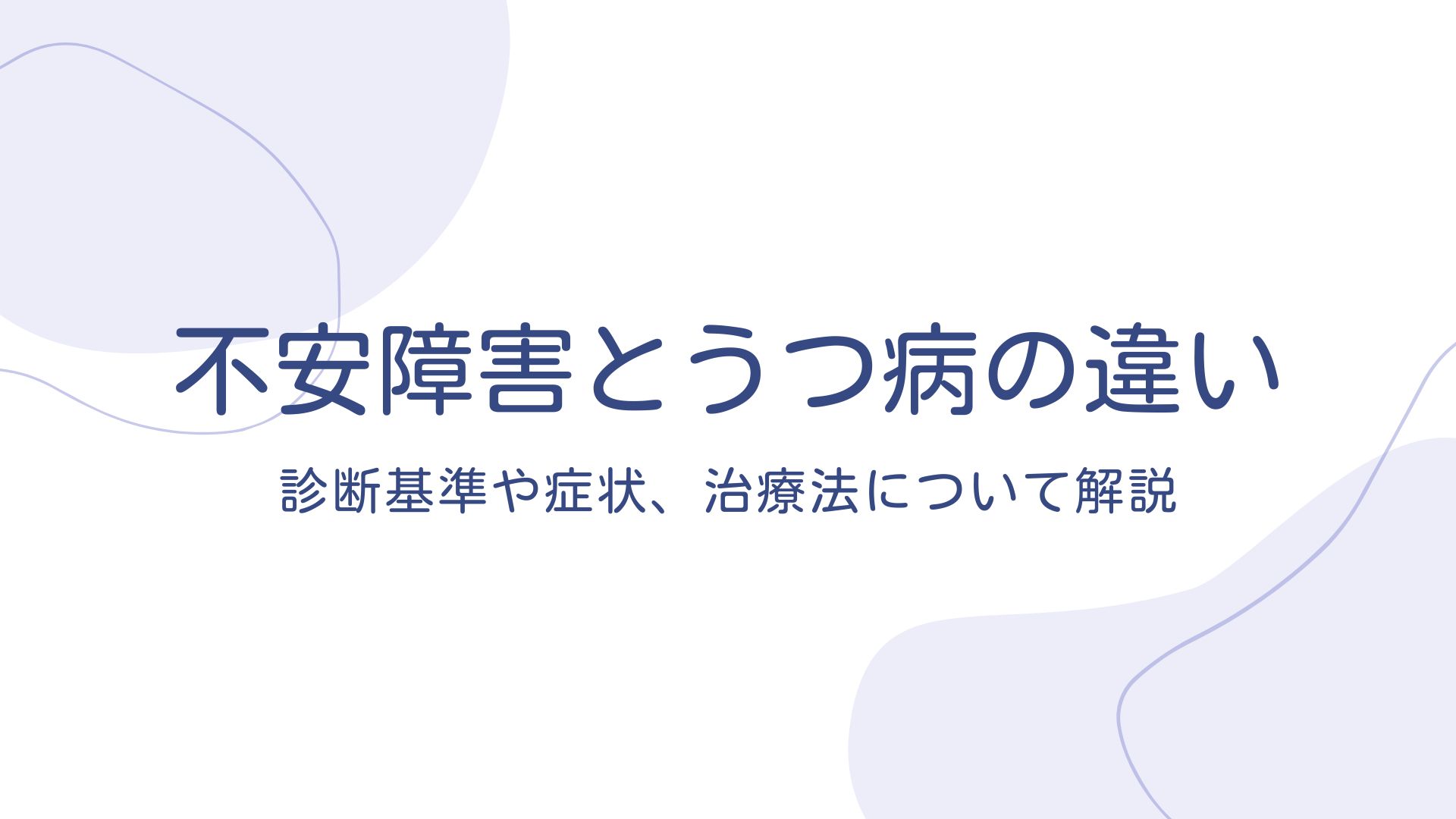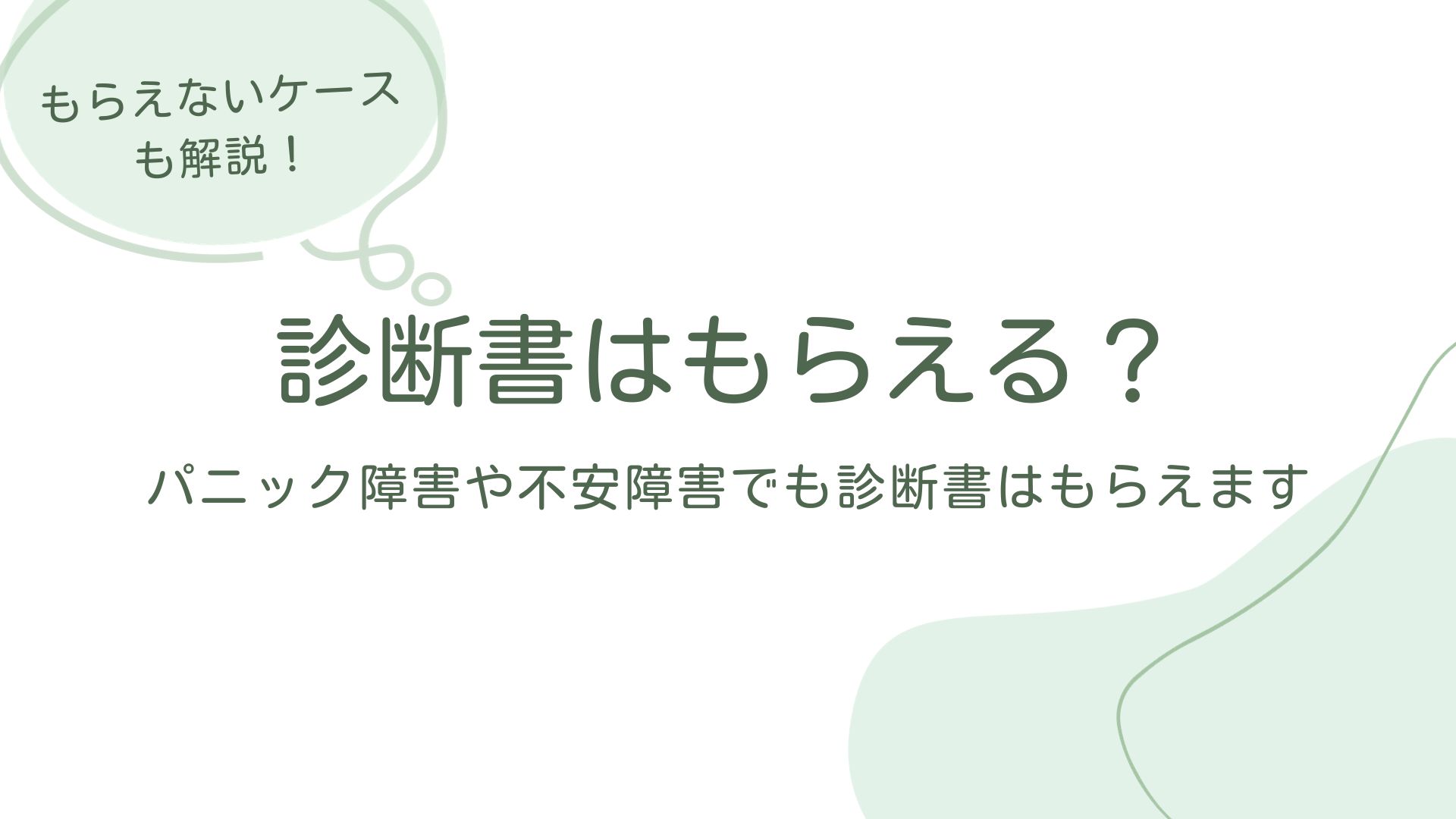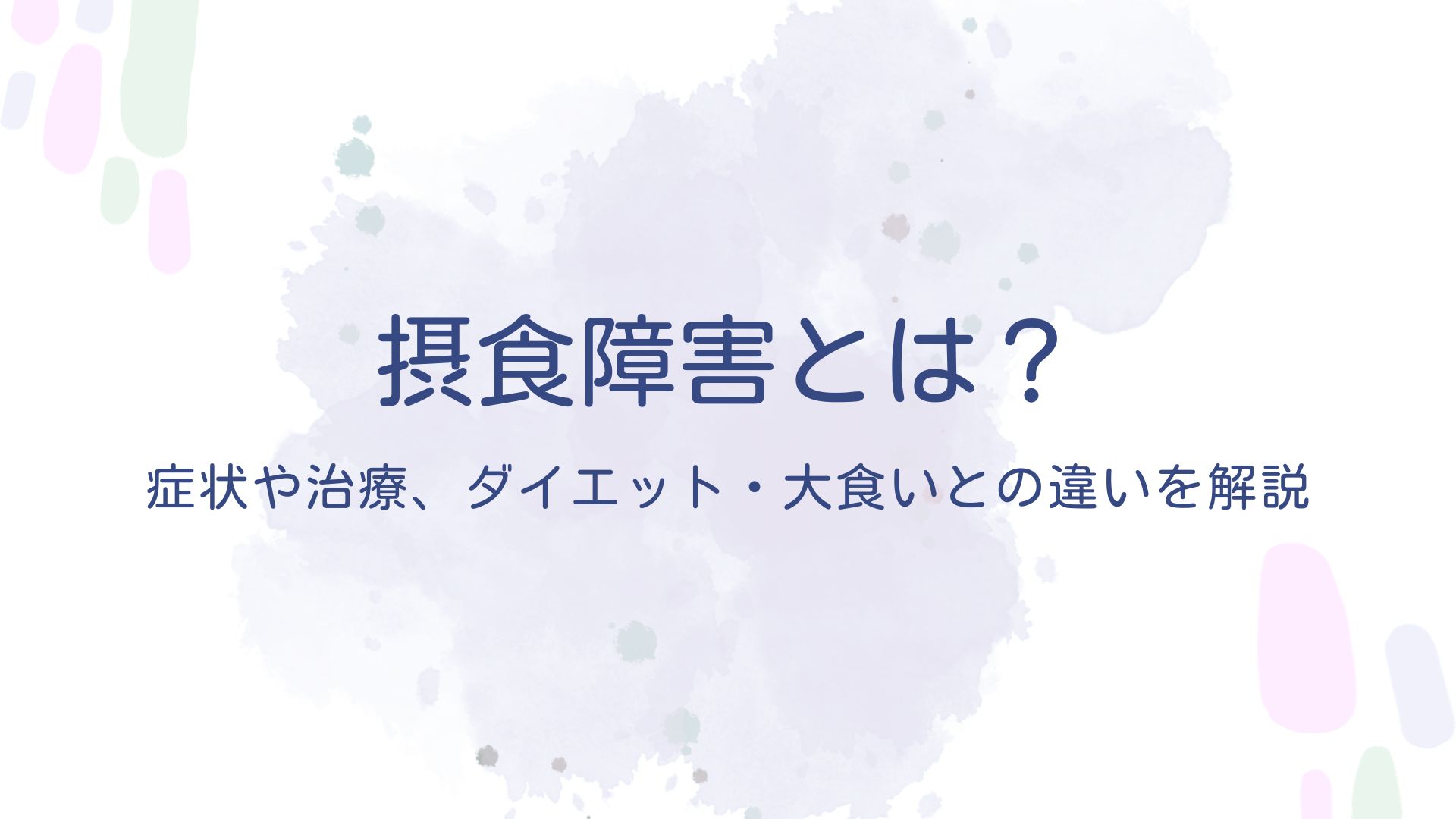Check*診断書発行が可能かどうかは医師の判断によるため発行が不可な場合もございます。本記事の傷病名での診断書はあくまで一例であり、診断はあくまで医師の判断によることをご了承ください。
「うつ病の診断書はすぐもらえる?」「うつ病の診断書をもらうための具体的な症状は?」「うつ病の診断書をすぐもらうための条件が知りたい」このような疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。
うつ病の診断書が発行されるタイミングは診断結果や医療機関によって異なります。そのため、医療機関を受診したからといって必ずしうつ病の診断書をすぐもらえるとは限りません。
この記事では、診断書がすぐにもらえるケースとそうではないケースについて紹介します。また、うつ病の診断書をすぐにもらうための具体的な症状例や診断書をもらうための流れについても詳しく解説していますので、参考にしてください。
なお、うつ病の診断書をすぐにもらうためには診断書の即日発行に対応した医療機関で診断を受ける必要があります。よりそいメンタルクリニックは当日の診断書発行に対応しているため、診断書が必要な方はご相談ください。
うつ病の診断書とは?

診断書とは、医師が患者に対して行った診断結果を記載した書類のことです。診断書をもらうことでうつ病であることの証明となります。うつ病の診断書をもらうためには専門医による診断が必要となります。
そのため、精神科や心療内科へ訪れて診察を受けて診断書作成の依頼をしてください。うつ病の診断書をもらうことで、仕事の休職や各種公的支援の申請が可能となります。うつ病を治すことに専念したい方や公的支援を利用したい方は診断書をもらうことをおすすめします。
うつ病の診断書はすぐもらえる?

うつ病の診断書をすぐもらえるかどうかは、診断結果や医療機関によって異なります。ここではうつ病の診断書がすぐもらえるケースと、すぐもらえないケースについて解説します。
診断書をすぐもらえるケース
診断書をすぐもらえるケースとして前提となるのが、うつ病と診断されることです。そのうえで、以下のような症状が見られる場合に診断書をもらえます。
- 休職して療養に専念する必要がある
- 休職が必要なほど症状が悪化している
- 休職によって症状の改善が期待できる
うつ病の症状が重く、直ちに休職が必要と判断された場合や休職を通じて病状の改善が期待できると認められた場合は診断書をすぐにもらえます。
診断書をすぐもらえないケース
診断書をすぐにもらえないケースとしては、以下の通りです。
- 一度の診断ではうつ病と断定できない
- うつ病だと断定できない
- 休職が必要なほどの状態ではない
- 症状についてしばらく様子をみる必要がある
- 診断書の発行に時間がかかる
気分がすぐれない、やる気がでないなどの症状は多くの方が経験のある症状です。そのため、うつ病は初診での判断がつきにくく、療養が必要と判断される症状が見られないと診断書が発行されないことがあるのです。
うつ病で診断書をすぐにもらえる具体的な症状例

うつ病で診断書をすぐにもらえる具体的な症状例を以下の3つのケースで紹介します。
- 職場で見られるうつ病のサイン
- 家庭で見られるうつ病のサイン
- 身体に見られるうつ病のサイン
それぞれの症状が見られる場合は、早急に医療機関を受診して診断書の発行を依頼しましょう。
職場で見られるうつ病のサイン
職場でのトラブルなどが原因でうつ病と判断された方の具体的な症状例は以下の通りです。
- パワハラを受けて強い自殺願望を抱えてしまう
- 朝目が覚めても身体が動かず、起きられない
- 会社に行く時に事故に巻き込まれたいと考えてしまう
上記の他にも職場で見られるうつ病のサインとしては仕事のストレスにより作業に集中できない、ミスが増えるといった症状が見られる場合があります。また、周囲の同僚とのコミュニケーションが減少し、孤立しがちになることもあります。
家庭で見られるうつ病のサイン
家庭で見られるうつ病の具体的な症状例は以下の通りです。
- 常に否定的な考えになってしまう
- 自傷行為を繰り返してしまう
- 気分がひどく落ち込み、家庭のことが何も手につかない
上記の他にも家事や育児などの日常活動へのやる気を失う、家族との会話や食事の機会が減少したなどの変化が見られる場合もあります。
身体に見られるうつ病のサイン
うつ病を発症すると心だけでなく身体にも症状が現れる場合があります。うつ病で身体に見られる具体的な症状例は以下の通りです。
- 自然と涙が出てくる
- 強い頭痛や動機が続く
- 食欲がなく体重が激減する
また、疲労感や倦怠感が常に続き軽い運動や日常的な動作ですら億劫になることもあります。これらの症状がみられた場合には、医療機関を訪れてすぐに診断書をもらうことをおすすめします。
うつ病は症状が進行すると、命に関わる行動につながる恐れがあります。職場・家庭・身体面で上記のサインが見られたら、よりそいメンタルクリニックに訪れて診断書をもらい早急に治療を開始してください。
うつ病の診断書の内容

うつ病の診断書に書かれる内容は医療機関によっても多少異なりますが、以下の表の内容が記載されることが一般的です。
| 病名 | 医師の診断で、その人の病名を記載します。 「うつ病」「双極性障害」などのはっきりとした病名だけでなく、「うつ状態」という曖昧な表現で記載されるケースもあります。 |
| 治療内容 | 治療の実施内容や通院の有無などを記載します。 |
| 治療期間 | 診断内容をもとに、どの程度の治療期間が必要かを記載します。 |
| 環境調整の見解 | 環境調整が必要な場合の具体的な見解について記載します。 例)「通院の継続が望ましい」や「自宅療養が望ましい」「配置の転換や異動が望ましい」 |
診断書には、診断結果に基づいて具体的な治療期間や休職の必要性などが記載されます。なお、治療期間にはうつ病の完治までの目安となる期間が書かれますが、あくまでも目安であるため症状の改善が見られなければ延長される場合もあります。
うつ病の診断書発行にかかる費用目安
うつ病の診断書発行にかかる費用は医療機関や診断内容によっても異なりますが、一般的には3,000円〜5,000円程度で発行が可能です。
ただし、うつ病の症状について細かな記載が求められる場合は10,000円程度の費用がかかる場合もあります。診断書発行のための具体的な費用が知りたい場合は、受診する医療機関の受付で確認することで明確な金額を確認できます。
うつ病の診断書が必要となる場面

うつ病の診断書が必要となる場面は、以下の通りです。
- 会社を休職するとき
- 公的機関による支援の申請をするとき
- 保険に関する手続きをするとき
それぞれの詳細を確認していきます。
会社を休職するとき
休職を申請するときにうつ病の診断書が必須となる場合があります。会社によっても異なりますが、診断書を提出することで休職が認められるケースが一般的です。
また、うつ病で会社を休職する場合は会社からの理解を得ることが大切です。可能であれば上司や経営者と直接面談しうつ病の症状の詳細や原因を説明することをおすすめします。うつ病の原因を理解してもらうことで、復職後の労働環境の改善につながるケースもあります。
公的機関による支援の申請をするとき
公的機関からの支援をもらう際もうつ病の診断書の提出が求められることが一般的です。診断書を提出してうつ病の症状が認められると、傷病手当金や自立支援医療制度など公的機関からの支援が受けられます。
うつ病で会社を休職している間も手当金や医療費の自己負担額の軽減など国からのサポートが受けられ、生活コストを軽減できるため早めに診断書を用意しておくと良いでしょう。
保険に関する手続きをするとき
生命保険の手続きを行う際もうつ病の診断書が必要となることが一般的です。診断書には、治療の進行状況や予後の見通しが記載されているため、保険会社が保険料の支払いの可否を判断する重要な資料となります。
診断書がないと生命保険を受け取れない恐れもあるため、保険料を受け取りたい場合は診断書の発行を依頼してください。
うつ病の診断書のもらい方

ここでは、うつ病の診断書のもらい方を4つの手順で解説します。
- 【ステップ1】精神科や心療内科を受診する
- 【ステップ2】医師の診察でうつ病の診断を受ける
- 【ステップ3】診断書の発行を依頼する
- 【ステップ4】発行された診断書を受け取って料金を支払う
医療機関を訪れてスムーズにうつ病の診断書をもらえるように、それぞれ確認しておきましょう。
【ステップ1】精神科や心療内科を受診する
診断書の発行ができるのは医師のみです。そのため、うつ病の診断書をもらうためには医療機関を受診して医師の診察を受ける必要があります。
心身の不調が続いていて仕事に行くのもままならない場合はうつ病の可能性がありますので、早めに精神科や心療内科がある医療機関を受診しましょう。
【ステップ2】医師の診察でうつ病の診断を受ける
診察時に現在の具体的な症状を医師に伝えましょう。患者から聞き取った症状によって、医師がうつ病かどうかの診断をします。
症状の詳細をうまく伝えられるようにあらかじめ自身の症状をメモでまとめておくと、自身の症状を具体的に伝えられます。
【ステップ3】診断書の発行を依頼する
うつ病の診断を受けたら、診断書をもらうことが可能です。このとき、本人が依頼しないと診断書はもらえません。
うつ病の診断書が欲しい場合は、発行の希望を必ず伝えてください。
【ステップ4】発行された診断書を受け取って料金を支払う
うつ病の診断書の発行に要する時間は医療機関によって異なります。その日にもらえることもあれば、後日受け取りが必要なこともあります。あらかじめ診断書の発行にかかる時間を調べておくとよいでしょう。
また、支払いについても同様で、その日もしくは受け取る日に必要になるかは医療機関によって異なります。
うつ病の診断書をもらうメリット

うつ病の診断書をもらうことでさまざまなメリットを得られます。ここでは診断書をもらう主なメリットを2つ紹介します。
- 治療に専念できる
- 公的な支援を受けられる
それぞれ確認していきます。
治療に専念できる
うつ病の診断書をもらうことで、休職して治療に専念できます。うつ病は、脳のエネルギーが不足して意欲が低下している状態です。疲れた脳をしっかり休ませるには、ストレスから離れてゆっくりと回復に専念することが必要となります。
診断書をもらい休職することで通院や自宅療養がしやすくなります。仕事に通いながらうつ病の治療をするのが困難な場合は、診断書をもらって休職することでうつ病の治療を進められるでしょう。
公的な支援を受けられる
うつ病で休職した場合に診断書をもらうことで、公的な支援を受けられる点も大きなメリットの1つです。
| 傷病手当金 | 病気やケガの療養で休業した場合、本人・家族に一定額が支給される |
| 自立支援医療制度 | 精神疾患の通院でかかる医療費の自己負担額が軽減される |
| 障害年金 | 病気やケガが原因で仕事が制限された場合に受け取れる年金 |
| 職場復帰支援(リワーク支援) | うつ病などで休職している人が、医師のアドバイスを受けながら職場復帰のサポートを得られる |
| 就労移行支援 | 就労を目指している場合、知識や技能などの訓練を受けられる |
| 精神障害者保健福祉手帳 | 精神障害の状態が認定され、公共料金の割引や税金の控除などの支援が受けられる |
休職中も金銭的な負担が軽減されるため、心理的なストレスが減りうつ病の改善につながります。休職中に金銭的な不安がある人や、今後復職を考えている人はぜひこれらの公的支援を活用してみましょう。
うつ病ですぐに診断書を書いてもらえないケースもある

医療機関に受診しても、以下の場合はすぐに診断書をもらえないため注意が必要です。
- クリニックが診断書の即日発効に対応していない
- 症状が曖昧でうつ病と判断できない
それぞれのケースについて確認していきます。
クリニックが診断書の即日発効に対応していない
医療機関によってはうつ病の診断書の即日発行に対応していない場合があります。明確にうつ病であることが診断されても診断書の即日発行に対応していない医療機関であると、その日のうちの診断書を受受け取れません。
そのため、うつ病の症状が明らかですぐに診断書を書いてもらいたい場合は診断書の当日発行に対応した医療機関に訪れる必要があります。
症状が曖昧でうつ病と判断できない
症状が曖昧でうつ病と判断できない場合はその日のうちに診断書を発行してもらえない場合があります。例えば、やる気が出ない、気分がすぐれないなど多くの方が経験する症状の場合はその日のうちにうつ病と判断することが難しく、症状の経過観察が必要となるケースがあります。
うつ病の診断書を即日もらうためには、うつ病の症状を明確に医師に伝える必要があるのです。
うつ病の診断書をすぐもらうための条件

うつ病の診断書をすぐにもらうためには、診断書の即日発行の可否を確認して受診することがポイントです。事前に医療機関へ確認してから受診しましょう。
初診時にうつ病と診断されるためには、具体的な症状を伝えることで当日の診断が可能となります。うつ病の診断書をすぐに欲しい場合は、以下のようなうつ病の具体的な症状があり療養が必要であることを説明してください。
- パワハラを受けて強い自殺願望を抱えてしまう
- 朝目が覚めても身体が動かず、起きられない
- 会社に行く時に事故に巻き込まれたいと考えてしまう
- 常に否定的な考えになってしまう
- 自傷行為を繰り返してしまう
- 気分がひどく落ち込み、家庭のことが何も手につかない
- 自然と涙が出てくる
- 強い頭痛や動機が続く
- 食欲がなく体重が激減する
また、うつ病は、国際的に用いられている「DSM-5」の診断基準に基づいて診断が行われることが一般的です。あらかじめ、「DSM-5」の診断基準を確認して、以下の基準に当てはまることを医師に伝えることもうつ病の診断書をすぐにもらうためのポイントです。
【診断基準】
A:以下の項目で「1・2」を含めた5つ以上の状態がほとんど毎日・2週間以上続き、日常生活や仕事場面で支障をきたしている。
B:Aに当てはまった項目は、ほかの病気や薬、アルコールなどの影響ではない C:Aに当てはまった項目は統合失調症、妄想性障害などの影響ではない D:落ち込んだり気分が高まったりを繰り返す躁うつ病(双極性障害)ではない |
参照:日本精神神経学会(日本語版用語監修)、髙橋 三郎 / 大野 裕(監訳)『DSM-5 精神疾患の診断・統計マニュアル』2014、医学書院
うつ病の診断書をすぐもらいたい方は、上記の条件を理解したうえであしたのクリニックまでご相談ください。
診断書がいますぐ欲しい方へ当院では受診いただ当日の診断書の発行(※)に対応しております。お困りの方はお気軽にご相談ください。
本日の受診も受付中です。詳しくは当院ホームページをご確認ください。
→新宿駅前の心療内科・精神科 あしたのクリニック
※医師が治療上必要と判断した場合のみ
うつ病の診断書をもらった後の会社へ伝える際のポイント

うつ病の診断書をもらった後は、上司に相談して休職の手続きをします。このときに就業規則をチェックして、休職制度について事前に確認しておくとスムーズに手続きを進められます。休職期間や給与の支払いについては、職場によってルールが異なるため注意しましょう。
また、休職中も定期的に職場との連絡が必要な場合があります。その際にどのような連絡手段と頻度でやり取りするのかを話し合っておきましょう。以下では、うつ病で休職する際の会社への伝え方のポイントを紹介します。
対面が難しい場合は電話やメールでも可能
うつ病で休職する場合は会社からの理解を得ることが大切です。可能であれば上司や経営者へ対面で相談をするようにしましょう。ただし、病状が重く対面での相談が難しい場合は、電話やメールでの連絡でも問題ありません。電話やメールで相談をする場合でも、診断書を会社へ送付することでうつ病の証明が可能です。
相談の際にはうつ病と診断されたことと、休職の必要性について丁寧な言葉で伝えてください。対面での相談が精神的に難しいからといって無断での休職は避けるようにしましょう。
症状の詳細を伝える
うつ病で会社を休職する際は診断書の提出だけでなく、症状の詳細やうつ病になった原因も説明してください。会社側が具体的な症状やうつ病になった原因を理解することで、職場環境の改善につながる場合があります。
また、症状に関する医師の見解や今後の見通しについても伝えることで会社も復職のタイミングを把握できます。
口頭でうつ病を伝える際はメモを用意しておく
うつ病の症状を口頭で伝える場合、緊張や不安でうまく伝えられないこともあります。そのため、伝えなければならないことを事前にメモしておくことで説明の漏れを防げます。
うつ病の診断書をもらうときによくある疑問

うつ病の診断書をもらって休職しようとするときに、心配になる点もいくつかあるでしょう。ここでは、診断書をもらう際によくある質問を2つ紹介します。
- 職場での評価に影響が出ることがある?
- 休職後の復職までに時間がかかる?
それぞれ確認して、疑問や不安の解消に役立ててください。
職場での評価に影響が出ることがある?
うつ病の診断書をもらって休職しようとすると、職場での評価が下がるのではないかと不安に思う人もいるでしょう。しかし、うつ病を隠したまま仕事を続けた場合余計に症状が悪化して、より重大なミスなどにつながる恐れがあります。
つまり、無理をして仕事を続けたとしても評価に悪影響が出る可能性が残ります。一方休職してうつ病の治療に専念し、調子が戻ったタイミングで復帰した場合、自身が健康に働けることで職場も安心して迎えられるなど、どちらにとってもメリットがあります。休職する際は自身の健康を優先し、療養に専念しましょう。
休職後の復職までに時間がかかる?
休職して仕事から離れると、復職が難しかったり、時間がかかったりするのではないかと心配する人もいると思います。たしかに、休職後の復職はプレッシャーがかかりやすく、うつ病の再発リスクもゼロではありません。
しかし、休職中は診断書の取得によって職場復帰に向けたさまざまな支援を受けられます。公的機関の支援を受ければ、復職に対する不安も軽減されるでしょう。休職して症状が落ち着くようになったら、ぜひ復職に向けた支援を受けてみましょう。
うつ病に関する具体的な症状を医師に説明しよう!
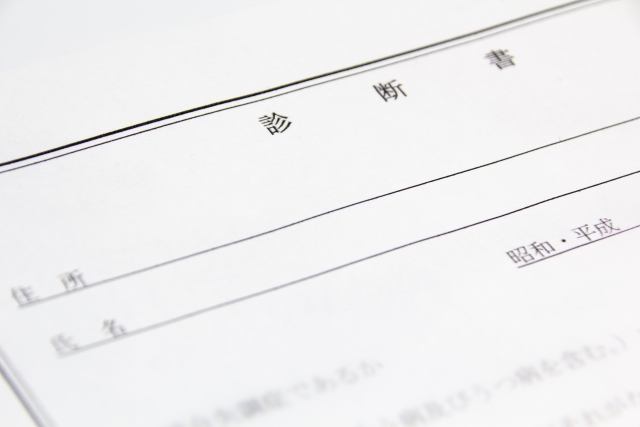
うつ病の診断書は症状が曖昧な場合や受診した医療機関が診断書の即日発症に対応していない場合はすぐに受け取れません。そのため、うつ病の診断書をすぐにもらうためには診断書の即日発症に対応している医療機関を受診して、うつ病だと診断される具体的な症状を医師に説明することが重要です。
よりそいメンタルクリニックでは受診いただいた当日の診断書発行に対応しているため、うつ病の診断書をすぐもらいたい方はお気軽にご相談ください。診断書を受け取り休職や公的機関の支援を受けてうつ病の治療を進めていきましょう。
参考サイト・文献
・日本精神神経学会日本語版用語監修、髙橋三郎ほか監訳:DSMー5精神疾患の診断・統計マニュアル、医学書院、2014
・こころの耳| 厚生労働省 – 3 うつ病の治療と予後
・厚生労働省|傷病手当金について
・厚生労働省|自立支援医療(精神通院医療)について
・日本年金機構|障害年金
・東京障害者職業センター|リワーク支援
・厚生労働省|こころの健康 サポートガイド
・こころの情報サイト|精神障害者保健福祉手帳
・厚生労働省|主治医と産業医の連携に関する有効な手法の提案に関する研究