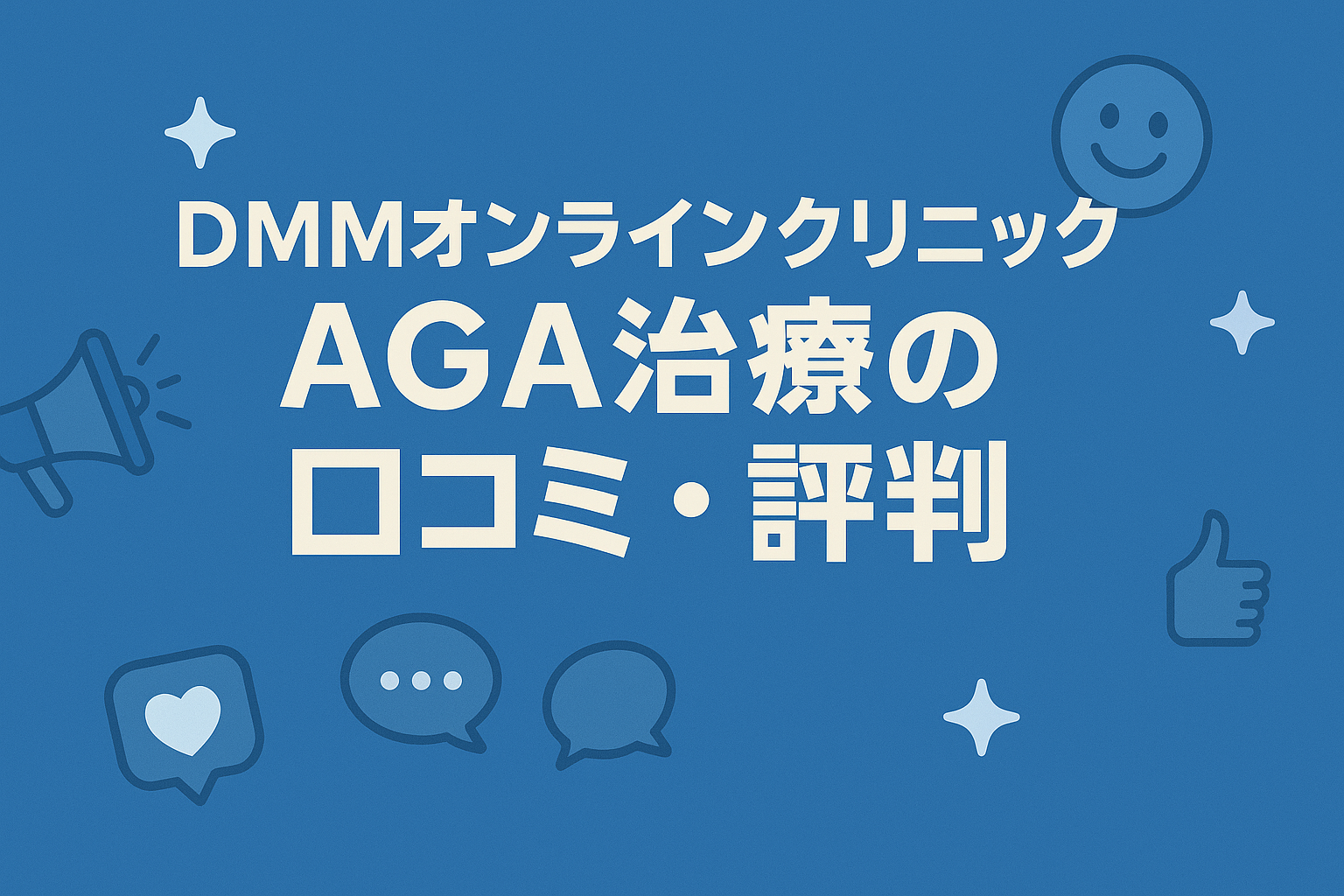「急に体調が悪くて会社を休みたい」「学校に提出する必要がある」「手当の申請が…」
様々な理由で、今すぐにでも診断書が必要になることがありますよね。特にメンタルの不調を感じているときは、心身ともにつらく、手続きのことまで考えるのは大変だと思います。
「診断書って、病院に行けばすぐもらえるもの?」
「心療内科や精神科でも、即日で発行してもらえるの?」
「休職したいけど、診断書がないと…」
そんな切実な疑問や不安を抱えている方も多いのではないでしょうか。
この記事では、診断書が「すぐもらえる」のか、特に精神科・心療内科での診断書発行の現実について、詳しく解説していきます。
この記事を読めば、診断書発行の基本的な流れから、スムーズに取得するためのヒント、そして知っておくべき注意点まで理解できます。焦る気持ちはわかりますが、まずは落ち着いて、正しい情報を知ることから始めましょう。
診断書がいますぐ欲しい方へ当院では受診いただいた当日の診断書の発行(※)に対応しております。お困りの方はお気軽にご相談ください。うつ病の診断書をすぐもらいたい場合もお気軽にご相談ください。
本日の受診も受付中です。詳しくは当院ホームページをご確認ください。
→新宿駅前の心療内科・精神科 よりそいメンタルクリニック
※医師が治療上必要と判断した場合のみ、当院書式のみ

以下求人ページからの直接のご応募で採用された方には、最大200万円のお祝い金を支給いたします。
まず知っておきたい、診断書の役割と発行の原則
診断書は、医師が患者さんの病状や治療内容などを証明する公的な書類です。主に以下のような場面で必要とされます。
- 休職・休学: 会社や学校に病状を説明し、療養に専念するため。
- 傷病手当金: 健康保険から給付金を受け取るため。
- 障害年金・障害者手帳: 公的な支援制度を利用するため。
- 保険金の請求: 生命保険や医療保険などの給付を受けるため。
- その他: 法的な手続きや各種申請など。
このように、診断書は社会的な手続きにおいて重要な役割を果たします。だからこそ、その発行には慎重さが求められ、「すぐもらえる」とは限らないのです。
なぜ診断書の即日発行は難しいのか?
- 正確な診断には時間が必要: 特に心の病気(精神疾患)の場合、症状は目に見えにくく、日によって波があることも少なくありません。医師は、患者さんの話をじっくり聞き、必要な検査を行ったり、一定期間の症状の経過を見たりして、慎重に診断を下します。急いで診断すると、誤診のリスクも高まります。
- 医師の専門的判断と法的責任: 診断は医師の高度な専門知識と経験に基づく判断であり、その内容には法的な責任も伴います。そのため、安易な発行はできません。
- 医療機関の事情: クリニックや病院の運用ルール、医師の診察スケジュール(多忙さ)などによって、書類作成に時間がかかる場合もあります。
特に精神科や心療内科では、初回の診察(初診)だけで確定診断を下すのは難しいケースが多く、問診だけでなく、心理検査を行ったり、数週間の経過観察が必要になったりすることもあります。
例外的?診断書が即日または比較的早く発行される可能性のあるケース
原則として即日発行は難しい診断書ですが、例外的に早く発行される可能性のあるケースも存在します。
- 医学的な緊急性が高い場合: 自分や他人を傷つけるリスクが非常に高い、あるいは重篤な身体症状(例:食事が全く摂れない、意識が朦朧としているなど)を伴う場合など、すぐに入院や休養が必要だと医師が判断した場合。
- 診断が比較的容易な身体疾患の場合: インフルエンザや骨折など、検査結果や症状から診断が明白な身体の病気の場合。ただし、これは精神科・心療内科以外のケースが主です。
- 継続通院中で症状が悪化した場合(再診): 以前から同じ病気で定期的に通院しており、その症状が明らかに悪化していると医師が判断した場合。すでに信頼関係があり、病状の経過を把握しているため、比較的スムーズに発行されることがあります。
重要な注意点:
これらのケースに当てはまる場合でも、最終的に診断書を発行するかどうか、いつ発行するかは、担当する医師の総合的な判断によります。「このケースだから絶対にもらえる」というわけではないことを理解しておきましょう。
うつ病・適応障害・発達障害…精神科・心療内科での診断書発行は「すぐもらえる」?
心の不調で診断書が必要な場合、特に気になるのが「うつ病や適応障害でもすぐもらえるのか?」という点だと思います。ここでは、代表的な精神疾患について、診断書発行の目安を見ていきましょう。
なぜ精神科・心療内科では時間がかかることが多いのか?
前述の通り、精神疾患の診断は慎重さを要します。その主な理由は以下の通りです。
- 症状が変動しやすい: 気分や体調は日によって、あるいは時間帯によっても変わることがあります。
- 客観的な指標が少ない: 血液検査や画像検査のように、数値や画像で明確に診断できる指標が少ないため、問診や行動観察が重要になります。
- 心理検査や経過観察の必要性: 正確な診断のために、心理検査を実施したり、一定期間(数週間~数ヶ月)症状の経過を見る必要があったりします。

うつ病・適応障害の場合

うつ病や適応障害の診断には、国際的な診断基準(DSM-5など)が用いられます。
例えば、うつ病の診断基準の一つには「抑うつ気分または興味・喜びの喪失が2週間以上続いていること」が含まれます。そのため、理論上は初診で「今日からうつ病です」と確定診断し、即日診断書を発行することは稀です。
しかし、以下のような場合は、比較的早期(数回の診察後など)に診断書が発行される可能性はあります。
- 症状が非常に重く、誰が見ても明らかに休養が必要な状態である。
- 職場環境などが原因で急激に症状が悪化した「急性ストレス反応」などが考えられる。
- 休職の必要性が差し迫っており、医師がその緊急性を認めた場合。
多くの場合、数回の診察を経て、症状の経過や持続性を確認した上で診断書が発行されると考えておくと良いでしょう。
自律神経失調症の場合
「自律神経失調症」は、特定の検査で異常が見つからないにも関わらず、めまい、動悸、倦怠感、不眠、頭痛、腹痛など、自律神経系のバランスが乱れることで起こる様々な不調を指す場合に用いられることがあります。
この診断は、他の身体疾患や精神疾患の可能性を除外した上で行われることが多いため、診断や診断書発行までに時間がかかる傾向があります。専門的な検査(心拍変動解析など)を行う医療機関もありますが、一般的には問診と経過観察が中心となります。
少しでも早く診断書をもらうために…受診前にできること・伝えるべきこと
診断書をできるだけスムーズに発行してもらうためには、受診する側にもできることがあります。ここでは、3つのヒントをご紹介します。
ヒント1:受診前にしっかり準備!「症状メモ」と「必要情報」

医師に的確に状況を伝えるために、事前に情報を整理しておきましょう。
- 症状メモ:
- いつから?: 症状が出始めた時期。
- どんな症状が?: 具体的な症状(例:「朝起きられない」「涙が出る」「集中できない」「動悸がする」など)。気分の波や体調の変化も。
- どのくらいの頻度・強さで?: 毎日続くのか、週に数回か。症状が最もつらい時を10とすると、どのくらいか。
- どんな時に悪化/改善する?: 特定の状況や時間帯など。
- 生活への支障: 仕事(遅刻、欠勤、ミス)、家事、学業、対人関係などで困っていること。
- きっかけ: 思い当たること(仕事の変化、人間関係の悩みなど)。
- 必要情報の確認:
- 診断書が必要な理由: (例:「会社に休職を申し出るため」「傷病手当金を申請するため」)
- 提出先: (例:「会社の人事部」「〇〇健康保険組合」)
- 必要な記載事項: 提出先によっては、特定の病名、休業が必要な期間(「〇月〇日から〇週間程度の休養を要す」など)、その他記載してほしい項目が決まっている場合があります。事前に確認しておきましょう。
- 持参するもの:
- 健康保険証
- お薬手帳(他の科で薬を飲んでいる場合)
- 紹介状(もしあれば)
- 上記の症状メモや必要情報のメモ
ヒント2:医師に正確に伝える「自分の状況」と「診断書の必要性」

診察時には、準備したメモを参考に、自分の言葉で正直に伝えましょう。
- 症状と困りごとを具体的に: 「つらい」「しんどい」だけでなく、「〇〇ができなくて困っている」「〇〇な症状で仕事に支障が出ている」など、具体的に伝えます。遠慮したり、見栄を張ったりせず、ありのままを話すことが大切です。
- 診断書が必要な背景を明確に: なぜ診断書が必要なのか、いつまでに必要なのか(もし期限があれば)を伝えます。「会社から、休職するには診断書が必要だと言われました」といった具体的な背景を伝えることで、医師も状況を理解しやすくなります。
【患者さんと医師の会話例】
患者さん: 「先生、実は1ヶ月ほど前から朝起きるのが非常につらくて、会社に遅刻することが増えてしまいました。仕事中も集中できず、簡単なミスを繰り返してしまって…。上司からも心配され、一度休んでしっかり治すように言われました。それで、休職の手続きのために、診断書が必要なのですが…」
医師: 「そうですか、詳しく教えてくださってありがとうございます。具体的に、いつ頃から、どんな症状でお困りなのか、もう少し詳しく聞かせてもらえますか? 会社には、診断書にどのような内容を記載する必要があるか確認されていますか?」
このように、具体的な状況や背景を伝えることで、医師は診断や必要な対応を判断しやすくなります。
国際的な考え方である「ICF(国際生活機能分類)」では、個人の健康状態(症状など)だけでなく、それを取り巻く環境(仕事の負荷、家庭環境など)や個人の背景(性格、価値観など)が相互に影響しあうと考えます。自分の状況をこの視点で整理し、「〇〇という環境(仕事のストレスなど)が、自分の△△という症状(不眠、意欲低下など)に影響して、□□という活動(出勤、業務遂行など)が難しくなっている」というように伝えられると、より医師に伝わりやすくなるかもしれません。
ヒント3:意外なポイント?「診断書発行実績」も確認【多くの方が見落としがちなポイント】
多くの方が見落としがちですが、医療機関によって診断書発行に関する方針や、手続きのスピード感に違いがある場合があります。
もちろん、最も重要なのは診断の質や医師との相性ですが、もし選択肢がある場合、以下のような視点も参考にできるかもしれません。
- 企業の産業医と連携しているクリニック: 企業の休職手続きなどに慣れている場合があります。
- ウェブサイトなどで診断書発行について明記しているクリニック: 発行に比較的慣れている可能性があります。
ただし、これはあくまで補助的な情報です。「診断書を早く出してくれる」ことだけを基準に医療機関を選ぶのは避け、信頼できる医師のもとで適切な診断・治療を受けることを最優先に考えましょう。

オンライン診療なら診断書はすぐもらえる?知っておきたいルールと現実
最近では、スマートフォンやパソコンを使って自宅から診察を受けられる「オンライン診療」も普及してきました。では、オンライン診療なら診断書はすぐもらえるのでしょうか?
オンライン診療での診断書発行ルール(初診・再診)

オンライン診療での診断書発行には、対面診療とは異なるルールがあります。
- 初診: 原則として、初診からオンライン診療のみで診断書(特に休職診断書など)を発行することは、慎重な判断が必要とされています。特に精神科領域では、対面での詳細な診察が重要視されるため、初診オンラインでの診断書発行に対応している医療機関は限られます。厚生労働省のガイドラインでも、対面診療を適切に組み合わせることが推奨されています。
- 再診: すでに同じ医療機関で対面診療を受けたことがある再診であれば、オンライン診療で診断書を発行してもらえる可能性は高まります。ただし、これも病状や診断書の種類によります。
2024年の医療法施行規則改正など、ルールは変化する可能性もありますが、現時点では「オンラインならすぐ診断書がもらえる」と安易に考えるのは難しい状況です。
うつ病などの精神疾患でオンライン即日発行は現実的か?
うつ病などの精神疾患の場合、初診のオンライン診療で即日診断書を発行してもらうのは、現時点ではかなり難しいと言わざるを得ません。診断の難しさや、なりすまし・不正取得のリスクなどを考慮すると、対面での慎重な評価が基本となります。
一部、オンライン診療に特化したクリニックも存在しますが、対応できる疾患や診断書の種類が限られている場合が多いです。
オンライン診療のメリット・デメリット

オンライン診療にはメリットもありますが、デメリットも理解しておく必要があります。
- メリット:
- 通院の手間や時間が省ける。
- 自宅などリラックスできる環境で受診できる。
- 遠方の専門医の診察を受けられる可能性がある。
- デメリット:
- 触診や一部の検査ができない。
- 通信環境に左右される。
- 対面診療に比べて情報量が少なく、診断精度に限界がある可能性。
- 対応できる疾患や処方できる薬が限られる場合がある。
- 診断書発行の条件が厳しい場合が多い。
オンライン診療を利用する場合も、これらの点を理解した上で、ご自身の状況に合っているか検討しましょう。
診断書の発行にかかる費用は?
診断書の発行は、病気の治療そのものではないため、健康保険が適用されず、全額自己負担(自費)となります。これは「文書作成料」として扱われます。
費用は医療機関によって自由に設定できるため、一概には言えませんが、一般的には数千円程度(例:3,000円~5,000円くらい)が目安となることが多いようです。複雑な内容や指定の書式がある場合は、もう少し高くなることもあります。
受診する前に、医療機関のウェブサイトで確認したり、電話で問い合わせたりしておくと安心です。
診断書発行に関するよくある質問 (Q&A)
ここでは、診断書の発行に関してよく寄せられる質問にお答えします。
Q1. 心療内科・精神科の初診でも診断書はすぐもらえますか?
A. 原則として難しいと考えてください。心の病気の診断には、症状の経過を慎重に見極める必要があるため、通常は初診のみで診断書を発行することは稀です。多くの場合、複数回の診察や、場合によっては心理検査などを経てから発行されます。
ただし、症状が非常に重い、緊急性が高いなど、医師が医学的に必要と判断した場合には、例外的に早期に発行される可能性もゼロではありません。まずは正直に症状や状況を伝え、医師に相談することが第一歩です。
Q2. 診断書の発行費用はいくらくらいですか?保険はききますか?
A. 診断書の発行は健康保険の適用外となり、全額自己負担(自費)です。費用は医療機関によって異なりますが、一般的には数千円程度が目安です。大学病院や、特殊な書式が必要な場合などは、それ以上かかることもあります。受診前に医療機関に確認することをおすすめします。
Q3. 診断書に書いてもらう内容(病名や休職期間など)は指定できますか?

A. 診断書に記載する病名や治療内容、休職が必要な期間などは、最終的には医師が医学的な根拠に基づいて判断します。患者さんの希望を伝えることはできますし、「会社から〇〇という期間で休職するように言われている」といった情報を伝えることは重要です。
しかし、医学的に妥当でない内容(例:実際よりも重い病名を書いてほしい、必要以上に長い休職期間を書いてほしいなど)を記載することはできません。医師は診察で得た客観的な所見に基づいて診断書を作成する義務があります。必要な記載事項(会社指定のフォーマットがあるか、休職期間の明記が必要かなど)があれば、事前に確認し、診察時に医師に正確に伝えましょう。
Q4. もし診断書の発行を断られたり、すぐにもらえなかったりしたらどうすればいいですか?
A. まずは焦らず、その理由を医師に確認しましょう。「まだ診断が確定していない」「もう少し症状の経過を見る必要がある」「情報が不足している」など、様々な理由が考えられます。理由を聞くことで、今後の見通しが立ったり、次回の診察で何を伝えればよいか分かったりするかもしれません。
それでも納得できない場合や、どうしても急いで診断書が必要な状況(例:会社からの最終通告など)であれば、他の医療機関でセカンドオピニオン(第二の意見)を求めるという選択肢もあります。
また、診断書がすぐに出ない状況を正直に会社や学校に説明し、相談することも大切です。「現在、医師の診察を受けており、診断書の発行にはもう少し時間がかかると言われています」と伝えるだけでも、状況を理解してもらえる場合があります。
大切なのは、主治医との信頼関係です。焦る気持ちはわかりますが、一方的に要求するのではなく、コミュニケーションを取りながら、ご自身の回復に向けて協力していく姿勢が重要です。
まとめ:診断書は「すぐもらえる」わけではない。焦らず、専門医に相談を
この記事では、診断書、特に精神科・心療内科領域での診断書が「すぐもらえる」のかどうか、そしてスムーズに取得するためのヒントについて解説してきました。
重要なポイント:
- 診断書は公的な書類であり、即日発行は原則として難しい、特に精神科・心療内科では正確な診断のために時間が必要。
- しかし、事前の準備(症状メモ、必要情報の確認)や、診察時に医師へ正確に状況を伝えることで、スムーズな発行につながる可能性はある。
- オンライン診療での診断書発行は、特に初診や精神科領域ではまだハードルが高いのが現状。
- 診断書の発行には自費で費用がかかる。
「診断書をすぐもらいたい」という焦る気持ちは、体調が悪い時ほど強くなるものです。しかし、最も大切なのは、焦って不確かな診断を求めるのではなく、信頼できる医師のもとで適切な診断を受け、ご自身の心と体を回復させることです。
もし、心身の不調を感じているなら、無理せず早めに専門の医療機関(心療内科、精神科など)を受診してください。どこに相談すればよいか分からない場合は、お住まいの地域の保健所や精神保健福祉センターなどに相談することもできます。
ご自身の健康を第一に考え、適切なサポートを得ながら、一歩ずつ進んでいきましょう。
免責事項:
本記事は、診断書の一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の医学的アドバイスや診断、治療に代わるものではありません。診断書の要否や内容、発行時期については、必ず担当の医師にご相談ください。また、医療制度やガイドラインは変更される可能性がありますので、最新の情報をご確認ください。