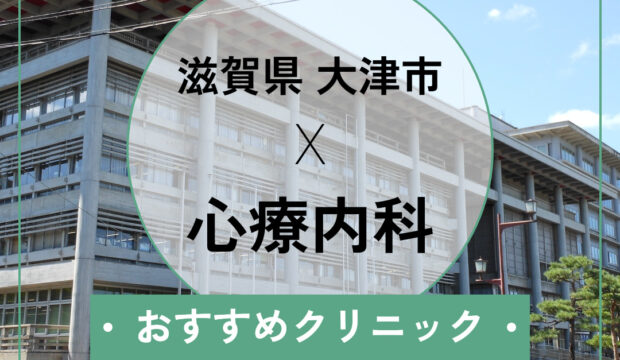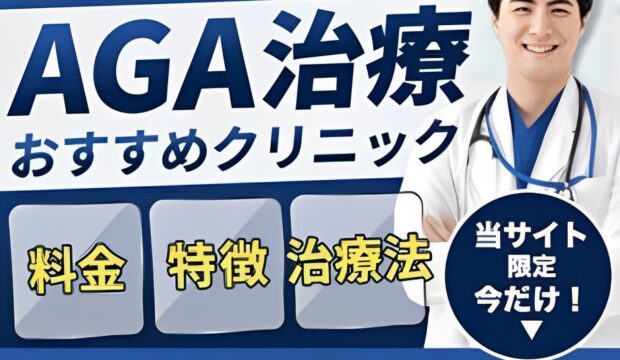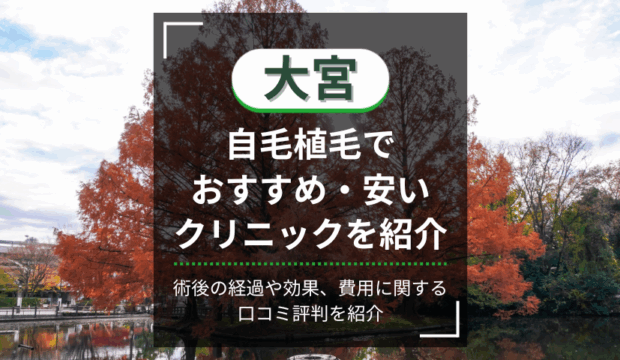ED(勃起不全)のお悩みを抱えながらも、「治療にはどのくらいの費用がかかるのだろう?」と不安に感じ、一歩を踏み出せずにいる方もいらっしゃるのではないでしょうか。「ED治療を受けたいけれど、やっぱり費用が心配…」「保険は使えるの?」「薬代は高いって聞くけど、実際いくらくらい?」こうした疑問は、多くの方が共通して持たれているものです。
この記事では、ED治療にかかる費用の全体像を詳しく解説します。治療費の内訳や平均的な相場、気になる保険適用のルール、そして主な治療薬の種類と値段(先発薬とジェネリック医薬品の違いを含む)について、分かりやすくお伝えします。さらに、オンライン診療の活用や費用を抑えるための具体的なヒントもご紹介します。
この記事を最後までお読みいただければ、ED治療の費用に関する疑問や不安が解消され、ご自身に合った治療法を安心して検討できるようになるはずです。
ED治療は原則「自由診療」

最も大切なポイントは、ED治療は原則として「自由診療」であるということです。自由診療とは、公的な医療保険(健康保険)が適用されない診療を指します。風邪や怪我で病院にかかる場合とは異なり、治療にかかる費用は全額自己負担となります。
自由診療であるため、治療内容や薬の価格はクリニックが独自に設定できます。そのため、同じ治療や薬であっても、クリニックによって費用が異なる場合があります。
ED治療費用の主な内訳

ED治療にかかる費用は、主に以下の3つで構成されます。
1. 診察料(初診料・再診料): 医師の診察を受けるための費用です。
2. 検査費用: EDの原因を特定するために、必要に応じて行われる検査の費用です。
3. 薬剤費: ED治療薬(内服薬)の費用です。
「結局、トータルでいくらかかるの?」という疑問が湧くかと思いますが、治療内容(必要な検査、処方される薬の種類や量など)によって費用は変動します。おおよその目安としては、初診時は数千円から1万円程度、継続治療の場合は薬剤費が中心となり、月額数千円から数万円程度となることが多いですが、これも個人差があります。
① 診察料(初診料・再診料)はいくら?無料のケースも?

診察料は、初めてクリニックを受診する際にかかる「初診料」と、2回目以降にかかる「再診料」があります。
- 初診料の相場: 一般的には0円(無料)から3,000円程度です。最近では、特にオンライン診療を提供しているクリニックを中心に、初診料を無料としているところも増えています。対面診療でも、薬の処方を受けることを条件に無料となるケースも見られます。
- 再診料の相場: 無料から1,500円程度が一般的です。継続的な治療を促すため、再診料を無料に設定しているクリニックが多い傾向にあります。
診察料の有無や金額はクリニックによって異なるため、受診前にウェブサイトなどで確認しておくと安心です。
② 検査費用:どんな検査が必要で、費用は?

EDの原因は様々であり、身体的な要因(糖尿病、高血圧、神経系の問題など)や心理的な要因が関わっています。原因を詳しく調べるために、以下のような検査が行われることがあります。
- 血液検査: 血糖値、コレステロール値、男性ホルモン値などを調べます。
- 超音波検査(エコー検査): 陰茎の血流状態を確認します。
ただし、すべての患者さんにこれらの検査が必要なわけではありません。 問診や簡単な診察で治療方針が決まることも多くあります。検査が必要と判断された場合の費用は、検査項目にもよりますが、数千円から1万円程度が目安です。
検査の必要性や内容、費用については、診察時に医師から説明があります。疑問や不安があれば、遠慮なく質問し、納得した上で検査を受けるようにしましょう。
③ 薬剤費:費用の大部分を占める薬の値段

ED治療費の中で、最も大きな割合を占めるのが「薬剤費」、つまりED治療薬の費用です。
現在、日本で処方されている主なED治療薬にはいくつかの種類があり、どの薬を選ぶか、どの用量(強さ)にするか、何錠処方してもらうかによって、費用は大きく変わってきます。そのため、ED治療の費用を考える上で、薬の値段について理解しておくことは非常に重要です。
次のセクションで、代表的なED治療薬の種類と、それぞれの値段について詳しく見ていきましょう。
ED治療薬の種類と値段:バイアグラ、シアリス…ジェネリックでお得に?
ED治療の主流は内服薬による治療です。日本でよく処方される代表的なED治療薬と、その価格について解説します。薬剤費は治療費の大部分を占めるため、「ED治療薬は高い」というイメージをお持ちの方もいるかもしれません。
代表的なED治療薬とその特徴

現在、日本で承認・処方されている主なED治療薬には、以下のものがあります。(※レビトラの先発品は販売中止となり、現在はジェネリック医薬品(バルデナフィル)が中心です)
| 種類(有効成分) | 特徴(効果発現時間、持続時間など) |
|---|---|
| バイアグラ (シルデナフィル) | ・服用後30分~1時間で効果発現 ・持続時間:約3~5時間 ・食事の影響を受けやすい |
| シアリス (タダラフィル) | ・服用後1~3時間で効果発現 ・持続時間:約24~36時間と長い ・食事の影響を受けにくい |
| レビトラ(ジェネリック) (バルデナフィル) | ・服用後15~30分と効果発現が早い ・持続時間:約5~8時間 ・食事の影響をやや受けやすい |
| ステンドラ (アバナフィル) | ・服用後約15~30分と効果発現が早い ・持続時間:約5~6時間 ・食事の影響を受けにくい |
これらの薬は、血管を拡張させて陰茎への血流を増やすことで勃起をサポートします。作用時間や食事の影響の受けやすさなどに違いがあるため、ご自身のライフスタイルや使用したい状況に合わせて、医師と相談しながら最適な薬を選ぶことが大切です。
先発医薬品とジェネリック医薬品の値段の違い

ED治療薬には、最初に開発された「先発医薬品」と、その特許期間が終了した後に、他の製薬会社が同じ有効成分で製造・販売する「ジェネリック医薬品(後発医薬品)」があります。
- 先発医薬品の価格帯: 1錠あたり 約1,200円~2,000円程度 が目安です。例えば、バイアグラ50mgで約1,200円強、シアリス20mgで約1,900円といった価格が見られます。
- ジェネリック医薬品の価格帯: 1錠あたり 約400円~1,600円程度 が目安です。先発医薬品と同じ有効成分でありながら、開発コストが抑えられているため、価格が安く設定されています。例えば、シルデナフィル(バイアグラのジェネリック)50mgで約900円、タダラフィル(シアリスのジェネリック)20mgで約1,400円~1,600円といった価格帯です。低用量であればさらに安価な場合もあります。
ジェネリック医薬品は、有効成分、効果、安全性において先発医薬品と同等であることが、厚生労働省によって厳しく審査・承認されています。そのため、品質を心配することなく、費用を抑えるための有効な選択肢となります。WEB検索結果の分析でも、ジェネリックの活用により年間16.8万円の費用削減が可能という試算があるほどです。
どの薬を選ぶかは、効果の相性やライフスタイル、そして費用面を考慮して、必ず医師と相談して決定しましょう。
ED治療は保険適用される?原則自由診療、例外ケースを解説
「ED治療に健康保険は使えないの?」という疑問は、多くの方が抱くことでしょう。結論から言うと、ED治療は原則として自由診療であり、健康保険は適用されません。
これは、EDが生命に直接関わる病気とはみなされにくく、QOL(生活の質)改善を目的とした治療と位置づけられているためです。そのため、加齢や心因性、生活習慣病(糖尿病や高血圧など)に伴うEDの治療は、全額自己負担となります。
例外的に保険適用となるケース:「不妊治療」

しかし、ごく一部ですが、例外的に保険適用となるケースがあります。それは、「不妊治療を目的としたED治療」の場合です。
2022年4月から、以下の条件を満たす場合に限り、ED治療薬の一部(バイアグラ、シアリスなど)の処方に保険が適用されるようになりました。
- カップルで不妊治療を受けていること: 医師が不妊症と診断し、治療計画に基づいている必要があります。
- 特定の医療機関であること: 不妊治療を行っているなどの施設基準を満たす医療機関である必要があります。
- 医師の要件: 泌尿器科に関する専門知識や5年以上の経験を持つ医師であることなどが求められます。
これらの条件を満たし、医師がED治療が不妊治療に必要と判断した場合に限り、保険適用(自己負担3割)となります。保険適用された場合、例えばバイアグラ50mgは1錠あたり約360円程度の自己負担で処方を受けられる計算になります。
ただし、この制度を利用できるのは、あくまで不妊治療中のカップルに限られます。不妊治療目的以外のED治療は、これまで通り自由診療となります。
ご自身が保険適用の対象となるかどうかは、自己判断せずに、必ず診察時に医師や医療機関に確認するようにしてください。
ED治療にかかる期間と総費用:継続治療のコスト感
ED治療は、薬を飲めばすぐに根本的に治るというものではなく、多くの場合、症状に応じて継続的な治療が必要となります。治療期間や、それに伴う総費用はどれくらいになるのでしょうか。
治療期間は人それぞれ

EDの原因や重症度、治療への反応性は人によって大きく異なります。そのため、治療期間も数ヶ月で改善が見られる人もいれば、年単位での治療が必要になる人もいます。
- 対症療法としての内服薬: ED治療薬は、根本的にEDを治すというよりは、性行為の際に勃起をサポートする対症療法として用いられることが一般的です。そのため、薬の効果が必要な時に都度服用する、という使い方を長期間続ける方も少なくありません。
- 原因へのアプローチ: 生活習慣病が原因であればその治療、心理的な要因が強ければカウンセリングなどを並行して行うことで、ED症状そのものが改善し、薬が不要になるケースもあります。
継続治療の費用目安

内服薬による治療を継続する場合、主に薬剤費がかかり続けることになります。
- 月額費用の目安: 使用頻度や薬の種類(先発薬かジェネリックか)によって大きく変動しますが、月額1万円~3万円程度が一つの目安とされています。ジェネリック医薬品を積極的に活用すれば、月額1万円以下に抑えることも可能です。
- 総費用のイメージ: ある調査では、ED治療を6ヶ月継続した場合の平均総費用は約94,000円というデータもあります。一方で、早期に治療を開始した方が、結果的に治療期間が短くなり、総費用を抑えられる可能性も指摘されています。
重要なのは、治療期間や費用について、事前に医師とよく相談し、無理なく続けられる治療計画を立てることです。「いつまで続ければいいのか」「総額でどれくらいかかりそうか」といった不安も、正直に医師に伝えてみましょう。ジェネリック医薬品の利用や、まとめ買いによる割引など、費用負担を軽減する方法についても相談できるはずです。
オンライン診療なら費用を抑えられる?メリットと注意点
近年、スマートフォンやパソコンを使って、自宅などから医師の診察を受けられる「オンライン診療(遠隔診療)」が普及し、ED治療でも利用する人が増えています。オンライン診療は、費用面でもメリットがあるのでしょうか?
オンライン診療のメリット

- 通院の手間が省ける: クリニックに行く時間や交通費がかかりません。
- プライバシーが保たれる: 人目を気にせず、自宅などでリラックスして診察を受けられます。
- 診察料が安い/無料の場合が多い: 多くのオンライン診療サービスでは、対面診療に比べて診察料(初診料・再診料)が安価、あるいは無料に設定されています。WEB検索結果の分析でも、オンライン診療実施機関の73%が診察料無料化を行っているというデータがあります。
- 薬が自宅に届く: 診察後、処方された薬が郵送で自宅などに届くため、薬局に行く手間も省けます。(別途送料がかかる場合が多い)
オンライン診療の費用構成とコスト削減効果

オンライン診療の費用は、主に「診察料(無料の場合も)+薬代+送料」で構成されます。診察料が無料または安価な場合が多く、交通費もかからないため、対面診療に比べてトータルの費用を抑えられる可能性があります。ある調査では、対面診療と比較して1回あたり平均3,500円程度のコスト削減効果が見られたという報告もあります。
DMMオンラインクリニックのように、複数のED治療薬を試せるセットプラン(例:3種セット3,960円~)を提供しているサービスもあり、コストを抑えつつ自分に合った薬を見つけたい場合に有用です。
オンライン診療の注意点
メリットの多いオンライン診療ですが、いくつか注意点もあります。
- 直接的な触診はできない: 画面越しの診察となるため、医師が直接体に触れて診察することはできません。
- 薬の到着に時間がかかる場合がある: 診察後、薬は郵送されるため、すぐに手元に欲しい場合には不向きなことがあります。特に地方在住の場合、配送に日数がかかる可能性も考慮しましょう。
- 対応クリニックを選ぶ必要がある: すべてのクリニックがオンライン診療に対応しているわけではありません。
オンライン診療は、特に「忙しくて通院する時間がない」「近くに専門クリニックがない」「対面での診察に抵抗がある」といった方にとって、有効な選択肢となり得ます。ただし、症状によっては対面での診察や検査が必要になる場合もあります。ご自身の状況や希望に合わせて、対面診療とオンライン診療のどちらが適しているか、医師とも相談しながら検討しましょう。
【実践】ED治療の費用負担を軽減する4つのヒント
ED治療は継続が必要な場合も多く、費用負担は決して軽いものではありません。ここでは、治療を無理なく続けるために、費用を少しでも抑えるための具体的なヒントを4つご紹介します。
ヒント1:ジェネリック医薬品を積極的に活用する
これが最も効果的で、多くの方に推奨できるコスト削減策です。前述の通り、ジェネリック医薬品は先発医薬品と同等の効果・安全性を持ちながら、価格が大幅に抑えられています。
- 具体例: 先発品のバイアグラが1錠1,200円程度するのに対し、ジェネリックのシルデナフィルなら900円程度、場合によってはさらに安価なものもあります。シアリスも同様に、ジェネリックのタダラフィルを選ぶことで費用を抑えられます。
- 年間の差: ある試算では、ジェネリックに切り替えることで年間約16.8万円もの費用削減につながる可能性も示されています。
- 分割処方も: クリニックによっては、錠剤を半分に割って用量を調整し、処方してくれる場合があります。これも費用を抑える工夫の一つです(ただし、自己判断で割るのは避け、必ず医師に相談してください)。
医師に相談する際に、「ジェネリック医薬品を希望します」と伝えることをためらう必要はありません。費用を抑えたいという意向を正直に話してみましょう。
ヒント2:クリニックを比較検討する
ED治療は自由診療のため、クリニックによって診察料や薬剤費が異なります。
- 比較ポイント: 初診料・再診料の有無、希望する薬(先発品/ジェネリック)の価格をチェックしましょう。ウェブサイトに料金表を掲載しているクリニックも多いです。
- 注意点: ただし、安さだけで選ぶのは禁物です。 医師の経験や専門性、説明の丁寧さ、クリニックの雰囲気、通いやすさ(立地や診療時間)なども考慮し、信頼できると感じるクリニックを選びましょう。特定疾患(糖尿病など)に対する割引制度を設けているクリニックもありますので、該当する場合は確認してみると良いでしょう。
ヒント3:まとめ買いやセットプランを利用する
クリニックによっては、薬を複数錠まとめて購入すると、1錠あたりの価格が割引になる「まとめ買い割引」や、複数の種類の薬を試せる「セットプラン」を用意している場合があります。
- メリット: 定期的に薬を使用する方にとっては、トータルの費用を抑えられる可能性があります。
- 注意点: ただし、一度に大量に購入しすぎると、使用期限が切れてしまったり、体調の変化で薬が合わなくなる可能性もあります。医師と相談の上、適切な量を購入するようにしましょう。
ヒント4:【意外なコツ】生活習慣を見直す
これは直接的な費用の割引ではありませんが、長期的に見て最も根本的なアプローチであり、結果的に費用削減につながる可能性があります。
- EDと生活習慣: 肥満、運動不足、喫煙、過度の飲酒などは、EDのリスクを高める要因となります。
- 改善の効果: バランスの取れた食事、適度な運動(特に有酸素運動)、禁煙、節酒などを心がけることで、血流が改善し、ED症状の軽減につながることがあります。
- 費用削減へのつながり: 生活習慣の改善によって症状が軽くなれば、薬の使用頻度や必要量が減り、結果として薬剤費の負担を長期的に減らすことができるかもしれません。ある研究では、生活習慣改善プログラムにより薬剤使用量が平均43%減少し、総治療費を抑制できたという報告もあります。
もちろん、生活習慣の改善だけでEDが完全に治るとは限りませんが、健康維持のためにも取り組む価値は十分にあります。何から始めればよいか分からない場合は、医師や管理栄養士などの専門家に相談してみましょう。
大学生も気になるED治療費用:若年層の現状と注意点
EDは中高年の悩みというイメージがあるかもしれませんが、実は大学生などの若い世代でもEDに悩む人は少なくありません。しかし、若い世代の場合、経済的な制約から治療に踏み切れない、あるいは費用面で無理をしてしまうケースも見られます。
若年層のED治療費用の実態
- 費用の捻出: アルバイト収入など、限られた収入の中から治療費を捻出している場合が多く、ある調査では20代患者の月額支出の平均は約8,300円というデータもあります。
- ジェネリック・オンライン診療の活用: 費用を抑えるため、ジェネリック医薬品の利用率が78%と高かったり、初診料が無料になることの多いオンライン診療の利用率が45%に達するなど、工夫している様子がうかがえます。
費用以外の障壁と悪循環
若い世代の場合、費用面だけでなく、「EDであることを他人に知られたくない」「恥ずかしくて相談できない」といった心理的な障壁が大きいことも特徴です。
この「恥ずかしさ」が受診をためらわせ、治療開始が遅れてしまうことがあります。治療開始が遅れると、症状が悪化したり、心理的な要因がさらに強固になったりして、かえって治療が長引き、結果的に総費用が増加してしまうという悪循環に陥る可能性も指摘されています(ある調査では、受診遅延により総費用が平均18.7万円増加したというデータも)。
若い世代へのアドバイス
- 一人で悩まない: EDは決して珍しいことではありません。一人で抱え込まず、勇気を出して専門医(泌尿器科)に相談することが解決への第一歩です。
- 利用しやすい選択肢: オンライン診療は、プライバシーを守りやすく、費用も抑えやすい傾向があるため、若い世代にとって利用しやすい選択肢の一つです。クリニックによっては学割制度などを設けている場合もあるかもしれません。
- 情報収集と比較: クリニックのウェブサイトなどで、費用体系やオンライン診療の有無などを確認し、自分に合ったクリニックを探してみましょう。
経済的な心配や恥ずかしさがあるのは当然ですが、放置して悩みが深くなる前に、まずは専門家に相談することをおすすめします。
ED治療の費用に関する疑問を解決!よくある質問 Q&A
ここでは、ED治療の費用に関して、特に多くの方が疑問に思われる点について、Q&A形式でお答えします。
- Q1: 初診だけでも費用はかかりますか?
- A1: はい、原則として初診料がかかるのが一般的です。ただし、最近では初診料を無料としているクリニックも増えています(特にオンライン診療)。事前にクリニックのウェブサイトなどで確認することをおすすめします。
診察の結果、問診のみで特に治療に進まなかった場合でも、診察行為に対する費用として初診料が発生することが通常です。こちらも念のため確認しておくと良いでしょう。 - Q2: 薬だけもらうことはできますか?その場合の費用は?
- A2: いいえ、原則として医師の診察なしにED治療薬だけを処方してもらうことはできません。 ED治療薬は、医師が患者さんの健康状態や他の服用薬などを確認した上で、処方の可否や適切な種類・用量を判断する必要がある「処方箋医薬品」です。
そのため、必ず医師の診察を受ける必要があります。オンライン診療の場合でも、ビデオ通話などを通じた医師の診察は必須です。費用としては、「診察料(無料の場合も)+薬剤費(+送料など)」が基本となります。
個人輸入などで安価に入手しようとする方もいますが、偽造薬や粗悪品のリスクが非常に高く、健康被害につながる恐れがあるため、絶対に避けるべきです。必ず医療機関で処方を受けてください。 - Q3: やはり保険適用で安くなることはほとんどないのでしょうか?
- A3: はい、残念ながらほとんどのケースでは保険適用されません。 前述の通り、例外は「不妊治療を目的としたED治療」の場合のみで、それもカップルでの治療や医療機関・医師の要件など、厳しい条件を満たす必要があります。
加齢や生活習慣病、心因性などが原因のED治療は、自由診療(全額自己負担)となります。ご自身が例外的なケースに該当するかどうかは、自己判断せず、必ず医師に相談・確認するようにしてください。 - Q4: ジェネリック医薬品は本当に効果や安全性が同じなのですか?費用が安い分、心配です。
- A4: ご心配になるお気持ちはよく分かります。しかし、ジェネリック医薬品は、厚生労働省によって先発医薬品と「同等の有効性・安全性」があると認められた医薬品です。
開発にかかる費用が少ないため安価に提供できますが、有効成分の種類や量、体への吸収のされ方などが先発品と同等であることを示すための様々な試験(生物学的同等性試験など)をクリアしています。国が定めた厳しい基準を満たしているため、安心して使用できます。
ジェネリック医薬品は、ED治療の費用負担を軽減するための非常に有効な選択肢です。もしジェネリック医薬品について不安な点や疑問があれば、遠慮なく医師や薬剤師に質問し、説明を受けて納得した上で使用するようにしましょう。
まとめ:ED治療の費用を知って、前向きな一歩を
今回は、ED治療にかかる費用について、その基本構造から内訳、保険適用のルール、薬の種類と値段、そして費用を抑えるためのヒントまで、詳しく解説してきました。
この記事のポイント:
- ED治療は原則「自由診療」で、保険適用は「不妊治療目的」など限定的。
- 費用は主に「診察料」「検査費用」「薬剤費」で構成され、特に薬剤費の割合が大きい。
- ED治療薬には先発医薬品とジェネリック医薬品があり、ジェネリックを選ぶことで費用を大幅に抑えられる。
- オンライン診療は、通院の手間や費用を抑える選択肢となり得る。
- 費用を抑えるには、ジェネリックの活用、クリニック比較、まとめ買いの検討、生活習慣の見直しなどが有効。
ED治療の費用は、クリニックや治療内容によって様々ですが、事前に費用の相場や内訳を知っておくことで、漠然とした不安はかなり軽減されるはずです。
費用面も含め、EDに関する悩みは一人で抱え込まず、まずは泌尿器科などの専門医に相談することが、解決への最も確実な第一歩です。医師はあなたの状態や希望(費用面も含め)を聞きながら、最適な治療法を一緒に考えてくれます。
ED治療は継続が必要な場合もありますが、医師とよく相談しながら、ご自身に合った治療計画・費用計画を立てていくことが大切です。この記事が、あなたが前向きな一歩を踏み出すための一助となれば幸いです。信頼できる医療機関を見つけ、安心して治療に取り組んでください。
免責事項:
本記事は、ED治療の費用に関する一般的な情報提供を目的としており、医学的なアドバイス、診断、治療を提供するものではありません。個々の症状や治療法については、必ず医師にご相談ください。また、医療制度や薬価は変更される可能性がありますので、最新の情報をご確認ください。