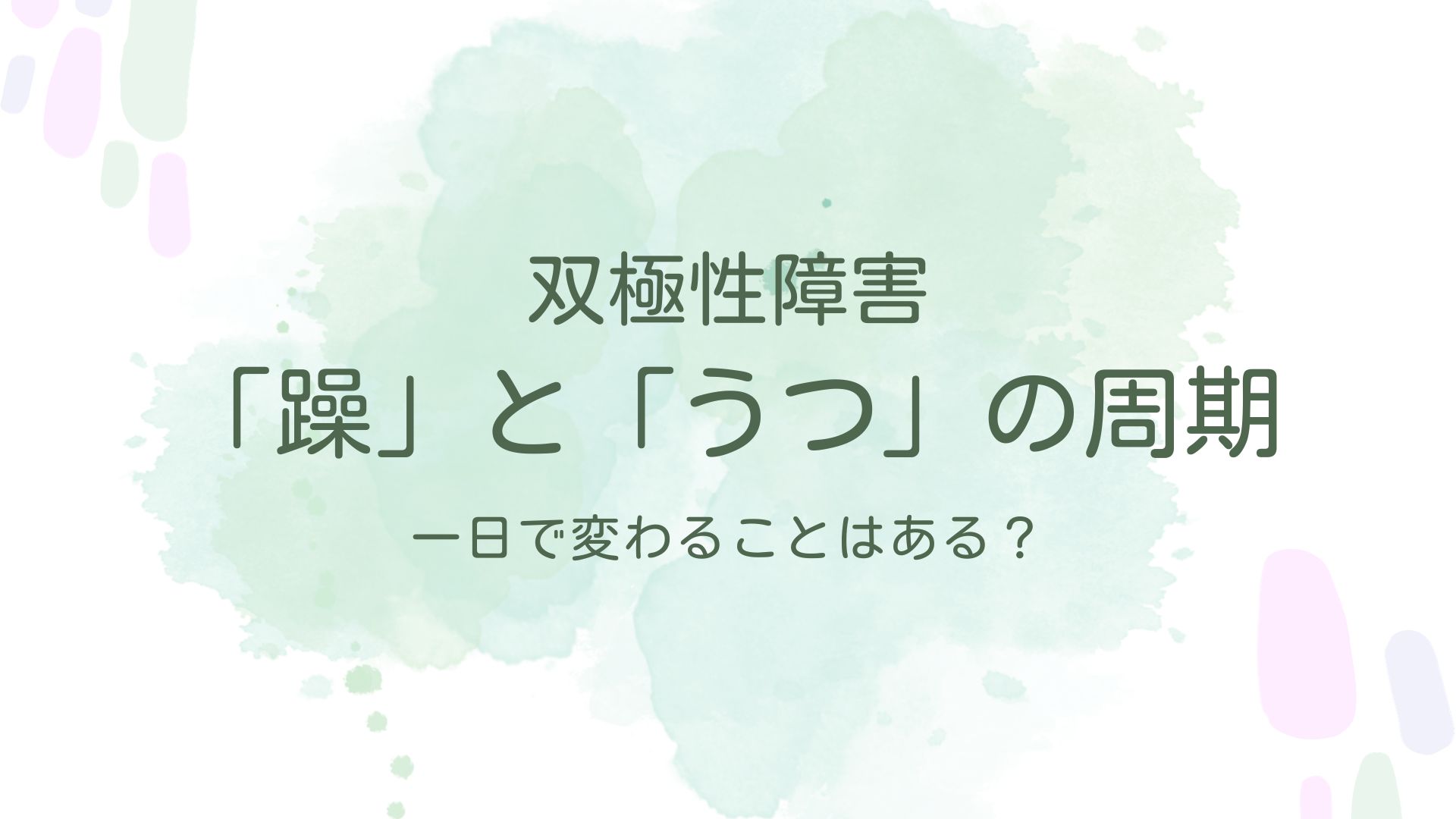「夜になると毎日腹痛が起こる」「眠ろうとするとお腹が痛くなる」という悩みは、多くの人が抱える症状のひとつです。
日中は平気でも、夜になると決まって腹痛が現れると、睡眠不足やストレスの悪循環につながり、日常生活に大きな影響を与えます。
原因としては、食事や生活習慣の乱れ、ストレスや自律神経の不調、さらには消化器系の病気(過敏性腸症候群・胃潰瘍・逆流性食道炎など)が考えられます。
本記事では、夜に毎日腹痛が起こる理由と考えられる病気、セルフチェックのポイント、そして改善につながる生活習慣や受診の目安まで詳しく解説します。夜の腹痛で悩んでいる方は、ぜひ参考にしてみてください。
夜になると毎日腹痛が起こる原因とは?

夜になると毎日腹痛が起こるのは珍しいことではなく、いくつかの要因が重なって生じることがあります。
日常の食生活や生活習慣の乱れ、ストレスや自律神経の不調、消化器系の病気、腸内環境の乱れ、さらに女性特有の要因など、さまざまな原因が考えられます。ここでは代表的な要因を順に解説していきます。
- 食生活や生活習慣による影響(暴飲暴食・冷え・就寝前の食事)
- ストレスや自律神経の乱れ
- 消化器系の病気(胃炎・胃潰瘍・逆流性食道炎)
- 腸のトラブル(過敏性腸症候群・便秘・腸内環境の乱れ)
- 女性特有の要因(月経・婦人科系疾患)
それぞれの詳細について確認していきます。
食生活や生活習慣による影響(暴飲暴食・冷え・就寝前の食事)
夜になると腹痛が起こる大きな要因のひとつに、食生活や生活習慣の乱れがあります。特に夕食での暴飲暴食や脂っこい料理の摂取は、胃腸に大きな負担をかけます。
また、就寝直前に食事をすると消化が追いつかず、横になることで胃酸が逆流しやすくなり、腹痛や胸やけを引き起こす原因になります。
さらに、冷たい飲み物やエアコンによる身体の冷えは、腸の血流を悪化させ、けいれん性の腹痛を招くことがあります。毎日夜になると腹痛が出る場合は、まず夕食の量や内容、食べる時間帯を見直すことが大切です。
できるだけ軽めで消化に優しいものを選び、就寝の2〜3時間前までに食事を済ませるよう心がけましょう。
ストレスや自律神経の乱れ
ストレスは胃腸に直結する大きな要因であり、夜になると毎日腹痛を感じる人の多くに関わっています。人間の自律神経は日中の活動時は交感神経、夜は副交感神経が優位になるのが正常なリズムです。
しかし、ストレスや不安を抱えていると交感神経が過剰に働き続け、腸の運動が乱れたり胃酸の分泌が増えたりして腹痛を引き起こします。
特に夜間はリラックスできず、ベッドに入った途端に不安が強まり、腸が過敏に反応することがあります。
こうしたストレス性の腹痛は過敏性腸症候群(IBS)にもつながりやすいため、リラクゼーションや深呼吸、入浴などで自律神経を整えることが大切です。毎日続く場合は心療内科での相談も選択肢に入れるとよいでしょう。
消化器系の病気(胃炎・胃潰瘍・逆流性食道炎)
夜に毎日のように腹痛が起こる場合、消化器系の病気が背景にあることも少なくありません。例えば、胃炎や胃潰瘍は胃酸の過剰分泌やピロリ菌感染などによって起こり、就寝中や空腹時に痛みが強く出ることがあります。
また、逆流性食道炎は横になると胃酸が食道へ逆流しやすくなり、胸やけやみぞおちの痛みを引き起こします。
こうした病気が原因の場合、市販の胃薬や整腸剤では根本的な改善が難しく、放置すると症状が悪化する可能性もあります。
毎晩決まって腹痛が起きるようであれば、内科や消化器内科で検査を受け、胃カメラや血液検査で正しい診断を受けることが重要です。早期に治療を始めれば生活の質も大きく改善されます。
腸のトラブル(過敏性腸症候群・便秘・腸内環境の乱れ)
腸のトラブルも、夜になると毎日腹痛を感じる大きな原因です。過敏性腸症候群(IBS)はストレスや食生活の影響で腸が過敏に反応し、下痢や便秘、ガスによる腹痛を繰り返します。
便秘が続いている場合、腸内にたまった便やガスが圧迫となり、特に横になったときに痛みを感じやすくなります。
また、腸内環境の乱れも影響します。バランスの悪い食生活や抗生物質の使用によって腸内細菌が偏ると、ガスが過剰に発生し腹痛を引き起こすのです。
こうした腸のトラブルを改善するには、食物繊維のバランスを整え、低FODMAP食を取り入れることや、発酵食品を適度に摂ることが有効です。腸内環境のケアを続けることで、夜間の腹痛が和らぐケースも多く見られます。
女性特有の要因(月経・婦人科系疾患)
女性の場合、夜になると毎日腹痛が出る背景には月経や婦人科系疾患が関与していることがあります。月経前や月経中はホルモンバランスの変化によって子宮の収縮が強まり、夜間に下腹部痛を伴うことがあります。
また、子宮内膜症や卵巣嚢腫といった婦人科系の病気は、周期的または慢性的な腹痛を引き起こしやすく、夜間に強く感じることも少なくありません。
これらの症状は放置すると悪化したり不妊につながったりするリスクもあるため、毎日繰り返す腹痛が生理周期や婦人科系の異常と関連している場合は、婦人科での検査が必要です。
自己判断せず専門医に相談することで、正しい診断と安心できる治療につながります。
夜になると毎日腹痛が起こる場合に考えられる病気

夜になると毎日腹痛が起こる場合、単なる生活習慣やストレスだけでなく、病気が隠れている可能性もあります。
特に消化器系や婦人科系の疾患は夜間に症状が出やすいことがあり、早めの受診が重要です。考えられる主な病気には以下のようなものがあります。
- 胃潰瘍・十二指腸潰瘍
- 過敏性腸症候群(IBS)
- 胆石・膵炎など消化器疾患
- 子宮内膜症など婦人科系疾患
- がん(胃がん・大腸がん)に注意すべきサイン
それぞれの詳細について確認していきます。
胃潰瘍・十二指腸潰瘍
胃潰瘍や十二指腸潰瘍は、胃酸や消化酵素によって胃や腸の粘膜が傷つき、炎症やただれが起こる病気です。
特徴的なのは「夜間や空腹時に強い腹痛が出る」ことで、寝ている間に痛みで目が覚める人もいます。原因としてはピロリ菌感染やストレス、鎮痛薬(NSAIDs)の長期使用などが知られています。
放置すると出血や穿孔といった合併症を引き起こす可能性もあるため、毎日夜になると痛みを感じる場合は、胃カメラ検査を受けて早期に診断することが大切です。
薬物療法で多くは改善しますが、再発予防のため生活習慣の見直しも欠かせません。
過敏性腸症候群(IBS)
過敏性腸症候群(IBS)は、腸に炎症や潰瘍などの異常がないにもかかわらず、下痢や便秘、腹痛などを繰り返す慢性的な腸の機能障害です。
夜になると腹痛が強くなる人も多く、特に一日の疲れやストレスが溜まった夕方以降に症状が悪化する傾向があります。下痢型・便秘型・混合型・ガス型などタイプによって症状は異なりますが、毎日同じ時間帯に腹痛が出ることも特徴のひとつです。
食事やストレスが大きく関係しており、低FODMAP食の実践や規則正しい生活が有効です。ただし自己判断が難しいため、消化器内科での相談をおすすめします。
胆石・膵炎など消化器疾患
胆石症や膵炎といった消化器系の病気も、夜間に腹痛を引き起こす原因となります。胆石が胆管に詰まると、右上腹部から背中にかけて鋭い痛みが走り、発作的に夜間に強い痛みが出ることがあります。
また膵炎はみぞおちや背中にかけて持続的な痛みを感じ、夜になると症状が悪化するケースもあります。これらの病気は吐き気や発熱、黄疸を伴うこともあり、放置すると命に関わる可能性もあるため注意が必要です。
毎日夜に腹痛がある場合でも「脂っこい食事の後に強い痛みが出る」「背中にまで痛みが広がる」といった特徴があるときは、できるだけ早く医療機関を受診しましょう。
子宮内膜症など婦人科系疾患
女性の場合、夜になると毎日のように腹痛が起こる背景には婦人科系疾患が関係していることもあります。代表的なのが子宮内膜症で、本来子宮内膜が存在しない部位に増殖することで強い下腹部痛を引き起こします。
特に月経周期に合わせて痛みが悪化しやすく、夜間や就寝中に腹痛で目が覚めるケースも珍しくありません。また、卵巣嚢腫や子宮筋腫なども腹部の圧迫感や痛みを伴うことがあります。
これらの疾患は不妊の原因になることもあるため、「夜だけ痛むから大丈夫」と放置せず、婦人科で検査を受けることが重要です。早期に治療を始めれば、症状の軽減や将来のリスク低減につながります。
がん(胃がん・大腸がん)に注意すべきサイン
毎日夜になると腹痛が続く場合、まれに消化器系のがんが関与していることもあります。胃がんや大腸がんは初期症状が乏しく、進行してから腹痛・体重減少・便の異常(血便・下痢・便秘の繰り返し)が現れるケースがあります。
特に「食欲不振」「体重が急に減った」「便に血が混じる」「夜間の腹痛が続く」といったサインがある場合は、注意が必要です。
がんは早期発見・早期治療が何よりも大切で、定期的な健診や内視鏡検査で見つけることができます。
毎日同じ時間に腹痛が起こるというのは身体からの重要なサインかもしれません。少しでも不安を感じたら、ためらわず専門医に相談しましょう。
夜間腹痛のセルフチェックポイント

夜になると毎日腹痛が起こる場合、原因を早期に見極めることが大切です。特に夜間に症状が強く出るときは、生活習慣や食事の影響だけでなく、消化器系や婦人科系の疾患が隠れていることもあります。
病院を受診する前に、まずは以下のセルフチェックで自分の症状を整理してみましょう。
- 痛みの部位(上腹部・下腹部・全体)
- 痛みの性質(差し込む・鈍い痛み・キリキリ)
- 便通の変化(下痢・便秘・血便)
- 食事との関係(就寝前の食事・アルコール)
- 他の症状(吐き気・発熱・体重減少)
それぞれの詳細について確認していきます。
痛みの部位(上腹部・下腹部・全体)
夜間腹痛をセルフチェックする際には、まず「どの場所に痛みを感じるか」を確認しましょう。
上腹部(みぞおち付近)の痛みは胃炎・胃潰瘍・逆流性食道炎などが考えられ、下腹部の痛みは過敏性腸症候群や便秘、女性では子宮内膜症や卵巣疾患が関与することがあります。
腹部全体に広がる痛みは腸炎や大腸の疾患などが疑われます。同じ腹痛でも部位によって原因が大きく異なるため、場所を具体的に把握することは診断の手がかりになります。
鏡の前で指差し確認をして「痛みが一番強いところ」を覚えておくと、病院での問診時にも役立ちます。
痛みの性質(差し込む・鈍い痛み・キリキリ)
夜間に腹痛が出る場合、その痛みの性質を観察することも大切です。差し込むような鋭い痛みであれば、胃潰瘍や胆石、腸閉塞など急性の病気が関係している可能性があります。
鈍く重い痛みは慢性的な炎症や便秘などに多く見られ、キリキリとした痛みは胃酸過多やストレス性の胃炎に関連することがあります。
また、痛みが「発作的に強くなるのか」「持続的に続くのか」でも病気の種類が分かれます。例えばIBSは差し込むような痛みが繰り返されることが多く、逆に膵炎などは持続的で強い痛みが特徴です。
自分の痛みを言葉にして記録する習慣が診断を早めます。
便通の変化(下痢・便秘・血便)
夜間腹痛とあわせてチェックしたいのが「便通の変化」です。下痢が続く場合は過敏性腸症候群や感染性腸炎が、便秘がひどい場合は腸閉塞や大腸の機能低下が疑われます。
また、便に血が混じる「血便」は痔だけでなく大腸がんや潰瘍性大腸炎など重い病気のサインであることもあるため要注意です。
便の形や色、回数をメモしておくと診断に役立ちます。特に「黒っぽい便(タール便)」は消化管出血の可能性があり、すぐに受診すべき症状です。
夜に腹痛が出て、翌朝に便通異常がある場合は、生活習慣の乱れだけでなく器質的な疾患を疑う必要があります。
食事との関係(就寝前の食事・アルコール)
「夜になると腹痛が出る」と感じる場合、直前の食事や飲酒との関連を振り返ることが重要です。寝る前に脂っこい食事や甘いものを食べると、消化に時間がかかり胃腸に負担をかけやすくなります。
また、アルコールは胃酸の分泌を増やし、胃粘膜を刺激するため、夜間に痛みを誘発する大きな要因となります。
食後すぐに横になる習慣も逆流性食道炎を悪化させ、みぞおちの痛みや胸やけを引き起こします。
症状が出るタイミングと食事内容を記録しておくことで、自己管理だけでなく医師に伝える際にも有効です。特に「毎晩同じ食品やお酒の後に痛む」という傾向がある場合は注意が必要です。
他の症状(吐き気・発熱・体重減少)
夜間腹痛に加えて他の症状がある場合、深刻な病気が隠れている可能性が高まります。吐き気や嘔吐を伴う場合は胃腸炎や膵炎、胆石などが考えられます。
発熱が続く場合は感染性腸炎や炎症性疾患の可能性があり、体重が急激に減少している場合は消化器系のがんを含む重篤な疾患のサインかもしれません。
特に「夜になると毎日腹痛+体重減少」という組み合わせは見逃してはいけない警告サインです。
これらの症状が併発している場合は、セルフケアや市販薬で様子を見るのではなく、できるだけ早めに医療機関を受診することが必要です。
夜の毎日の腹痛で受診を検討すべきサイン

夜になると毎日腹痛が起こる場合、生活習慣や食事内容が原因のこともありますが、病気が隠れている可能性も否定できません。
特に以下のサインがあるときは、自己判断で放置せず、できるだけ早めに医療機関を受診することが大切です。
- 強い痛みで眠れない
- 毎日続く・2週間以上改善しない
- 血便や吐血がある
- 急激な体重減少や食欲不振
- 市販薬や生活改善で改善しない
それぞれの詳細について確認していきます。
強い痛みで眠れない
夜間の腹痛が強く、眠れないほどの状態が続く場合は、重大な疾患が隠れている可能性があります。
通常の胃腸の不調であれば横になって安静にしているうちに和らぐこともありますが、痛みで夜中に目が覚めたり、寝返りが打てないほどの苦痛がある場合は要注意です。
胃潰瘍や膵炎、腸閉塞など緊急性を要する病気が関与している場合もあり、放置すると悪化して命に関わるケースもあります。
眠れないほどの腹痛が毎晩続くと、身体の疲労や免疫低下を招き、さらなる体調悪化につながります。夜間救急の利用も含めて、早めに受診する判断が必要です。
毎日続く・2週間以上改善しない
夜の腹痛が一過性のものであれば、食べすぎや冷えなどが原因で自然に改善することもあります。しかし「毎日続く」あるいは「2週間以上改善しない」という場合は、慢性的な病気の可能性が高いです。
例えば過敏性腸症候群(IBS)、胃炎、潰瘍、婦人科系疾患などは長期的に症状が現れることがあります。特に同じ時間帯に痛みが繰り返される場合、体内リズムや自律神経の影響も考えられます。
慢性的な腹痛を放置すると、消化器官の炎症が悪化したり、生活の質が大きく下がるリスクがあります。2週間以上続いているときは自然治癒に期待せず、消化器内科などで検査を受けることが大切です。
血便や吐血がある
夜間の腹痛に加えて、便に血が混じる「血便」や、吐いたものに血が混ざる「吐血」がある場合は、消化管出血が起きている可能性が高く、非常に危険です。
胃潰瘍や十二指腸潰瘍、大腸ポリープ、大腸がんなどの重大な疾患が原因であることがあります。
血便は痔でも起こりますが、鮮やかな赤い血か、黒っぽいタール状の便かによって原因は異なり、特に黒っぽい便は上部消化管からの出血を示唆するため緊急受診が必要です。
吐血の場合も同様に、胃や食道に重大な損傷がある可能性があります。これらの症状は自然に治まることはほとんどなく、放置すれば貧血やショック状態を引き起こすこともあるため、すぐに病院に行くべきサインです。
急激な体重減少や食欲不振
夜の腹痛に加えて「急激な体重減少」や「食欲不振」がある場合は、消化器系のがんや慢性的な炎症性疾患が関与していることがあります。
特に数週間〜数か月の短期間で体重が数キロ以上減少している場合は要注意です。食欲不振は胃や腸の機能低下だけでなく、精神的なストレスによっても起こりますが、腹痛と同時に進行している場合は器質的疾患を疑う必要があります。
がんや難病の場合、初期症状は軽度の腹痛や違和感にとどまることもあり、気づかないうちに進行しているケースも少なくありません。
自己判断でダイエットや生活習慣のせいと片づけず、消化器内科や総合病院で精密検査を受けることが望まれます。
市販薬や生活改善で改善しない
胃腸の不調による一時的な腹痛であれば、胃薬や整腸剤を飲んだり、食生活を整えることで改善することが多いです。
しかし、市販薬を数日〜1週間試しても症状が軽減しない場合や、生活改善(規則正しい食事・睡眠・ストレス軽減)をしても腹痛が続く場合は、自己ケアでは対応できない病気が隠れている可能性があります。
例えば、慢性胃炎や逆流性食道炎、IBS、大腸疾患などは根本的な治療が必要です。特に市販薬を飲んでも効かない症状は「原因が薬でカバーできない病態」であることを示しています。
自己判断で薬を続けるのではなく、早めに病院で専門的な検査を受けることが重要です。
夜の腹痛を和らげる生活改善法

夜になると腹痛が起こる場合、必ずしも病気が原因とは限らず、生活習慣を見直すことで改善するケースも多くあります。
特に以下のポイントを意識することで、夜間の腹痛を軽減しやすくなります。
- 就寝前の食事を控える(食べるなら消化の良いもの)
- カフェイン・アルコール・脂っこい食事を避ける
- ストレス対策(深呼吸・軽いストレッチ・リラックス)
- 腸に優しい食事習慣(低FODMAP・発酵食品)
- 睡眠環境を整える(冷え対策・寝姿勢)
それぞれの詳細について確認していきます。
就寝前の食事を控える(食べるなら消化の良いもの)
夜遅くに食事をとると、消化器官が休む時間に働き続けることになり、胃や腸に負担がかかります。その結果、消化不良や胃酸の逆流が起こり、腹痛や胃もたれにつながることがあります。
どうしても就寝前に食べる必要がある場合は、脂っこい料理や刺激物は避け、消化の良いおかゆやうどん、バナナなどを少量にとどめることが大切です。
また、横になるまで最低でも2〜3時間の間隔をあけることで胃腸への負担を軽減できます。
食べ方にも工夫が必要で、早食いや詰め込みは消化を妨げるため、よく噛んでゆっくり食べることが夜間腹痛の予防につながります。
カフェイン・アルコール・脂っこい食事を避ける
夜間に腹痛を引き起こしやすい食事として代表的なのが、カフェインやアルコール、脂っこい料理です。カフェインは胃酸の分泌を促し、胃粘膜を刺激して痛みや胃もたれを悪化させます。
アルコールも同様に胃や腸を荒らしやすく、就寝中の腹痛や下痢を引き起こす要因になります。また、揚げ物やラーメンなど脂質の多い食事は消化に時間がかかり、睡眠中も胃が働き続けることで不快感や痛みを誘発します。
夕食はなるべく軽めに、温かく消化の良い和食を中心にするのがおすすめです。夜間腹痛を繰り返す人は、これらの食品を避けることで症状の改善を実感しやすくなります。
ストレス対策(深呼吸・軽いストレッチ・リラックス)
ストレスは自律神経を乱し、腸の働きにも大きく影響します。特に副交感神経が優位になる夜に、自律神経のバランスが崩れていると、腸の過剰な収縮が起こり腹痛につながることがあります。
そこで効果的なのが、就寝前のストレスケアです。深呼吸や瞑想で呼吸を整えると、副交感神経が安定しリラックスしやすくなります。
また、軽いストレッチやヨガは血流を促し、胃腸の緊張を和らげる働きがあります。
音楽やアロマを取り入れるのも有効です。ストレスをため込まない生活習慣を意識することで、夜間の腹痛を予防でき、質の高い睡眠を得られるようになります。
腸に優しい食事習慣(低FODMAP・発酵食品)
腸内環境を整えることは、夜間腹痛の改善に直結します。特に「低FODMAP食」は過敏性腸症候群(IBS)の人に有効とされ、玉ねぎやにんにく、小麦などのガスを発生しやすい食品を控えることで腹部の張りや痛みを軽減できます。
また、乳酸菌やビフィズス菌を含むヨーグルトや味噌、納豆などの発酵食品は腸内フローラを改善し、消化吸収を助ける働きがあります。
ただし、乳糖不耐症の人は牛乳やヨーグルトで逆効果になる場合があるため、無乳糖製品や豆乳ヨーグルトを選ぶと安心です。腸にやさしい食生活を意識することで、腹痛だけでなく便通や全身の健康にも良い影響を与えます。
睡眠環境を整える(冷え対策・寝姿勢)
睡眠中の体の冷えや寝姿勢も、夜間の腹痛に影響を与える大きな要因です。腹部が冷えると腸の動きが不安定になり、痛みや張りを引き起こしやすくなります。
冬場はもちろん、夏場も冷房の風でお腹が冷えることがあるため、腹巻きや薄手のブランケットで対策すると効果的です。
また、寝姿勢にも工夫が必要で、仰向けでまっすぐ寝るよりも、左側を下にして横向きで眠ると胃の内容物が逆流しにくくなり、胃酸による腹痛を予防できます。
枕の高さを少し調整して上半身を起こすのも有効です。冷えと姿勢を意識して睡眠環境を整えることで、夜間腹痛の改善につながります。
医療機関での検査と治療方法

夜になると毎日のように腹痛が起こる場合、自己判断だけでは原因を特定できないため、医療機関での検査が重要になります。
内科や消化器内科、場合によっては婦人科で専門的な診断と治療を受けることが必要です。主な検査・治療方法は以下の通りです。
- 内科・消化器内科で受けられる検査(血液・内視鏡・超音波)
- 薬物療法(制酸薬・整腸剤・鎮痛薬)
- 食事療法と生活指導
- 婦人科での検査と治療(女性の場合)
それぞれの詳細について確認していきます。
内科・消化器内科で受けられる検査(血液・内視鏡・超音波)
内科や消化器内科では、まず血液検査で炎症反応や貧血の有無を調べ、消化管に異常がないかを確認します。さらに胃や十二指腸の潰瘍、逆流性食道炎、大腸疾患の可能性を探るために、内視鏡検査(胃カメラ・大腸カメラ)が行われます。
内視鏡は直接粘膜の状態を観察でき、組織を採取して病理検査を行うことも可能です。
加えて、腹部超音波検査(エコー)は胆石や膵炎などの診断に役立ち、放射線被ばくのない安全な検査として広く利用されています。
症状や年齢、リスク因子に応じて検査の種類は選択され、正確な原因特定につながります。
薬物療法(制酸薬・整腸剤・鎮痛薬)
検査結果に基づき、腹痛の原因に応じた薬物療法が行われます。胃酸の逆流や胃潰瘍が原因の場合は、プロトンポンプ阻害薬(PPI)やH2ブロッカーといった制酸薬が処方され、胃酸の分泌を抑えて粘膜の修復を助けます。
過敏性腸症候群(IBS)では、腸の運動を整える整腸剤や、腸内環境を改善するプロバイオティクス製剤が有効です。
強い痛みに対しては、鎮痛薬や鎮痙薬が補助的に用いられる場合もあります。ただし、鎮痛薬の乱用は逆に胃腸に負担をかけるため、医師の指導に従って使用することが大切です。
薬物療法はあくまで対症療法であるため、生活習慣の改善と併せて行うことが推奨されます。
食事療法と生活指導
夜間腹痛を改善するためには、薬だけでなく日常生活の見直しも欠かせません。消化に良い食事を心がけ、脂質や刺激物、アルコールを控えることが基本となります。
さらに過敏性腸症候群の人には、低FODMAP食と呼ばれる食事法が有効で、ガスの発生や腸内の不快感を軽減する効果があります。
また、食べる時間や量も重要で、就寝直前の食事は避け、腹八分目を意識することが勧められます。加えて、ストレスが症状悪化に直結することも多いため、医師や栄養士の指導のもとで生活改善を取り入れることが必要です。
これらを継続的に行うことで、薬の効果を補い、腹痛の再発予防にもつながります。
婦人科での検査と治療(女性の場合)
女性の場合、夜間の腹痛が婦人科系疾患に由来しているケースも少なくありません。特に子宮内膜症や卵巣嚢腫は、夜間や生理前後に強い下腹部痛を引き起こすことがあります。
婦人科では内診や超音波検査、必要に応じてMRIなどの画像検査を行い、病気の有無を確認します。治療はホルモン療法や鎮痛薬の使用が中心となりますが、重症例では手術が検討される場合もあります。
また、生理周期との関連を記録しておくと診断に役立つため、症状日誌を持参すると良いでしょう。婦人科的な原因が疑われるときは、消化器内科だけでなく婦人科の受診も並行して行うことが望まれます。
家族や周囲ができるサポート

夜になると毎日のように腹痛が起こる人にとって、家族や周囲の理解と協力は大きな支えとなります。症状は目に見えにくいため軽く扱われがちですが、実際には生活の質を大きく下げてしまう深刻な問題です。
本人だけで抱え込まず、周囲が正しく関わることで安心感を与え、医療機関への受診や生活改善の継続にもつながります。家族や周囲ができる主なサポートは以下の通りです。
- 症状を軽視せず話を聞く
- 病院受診を勧める
- 食事や生活リズムを一緒に整える
- 無理をさせないようサポートする
それぞれの詳細について確認していきます。
症状を軽視せず話を聞く
腹痛は外から見えない症状のため、周囲が軽く受け止めてしまうこともあります。しかし「気のせい」「少し休めば治る」といった言葉は本人を追い詰め、症状悪化の原因になることもあります。
まずは「毎日つらい思いをしている」という気持ちを理解し、しっかりと耳を傾けることが大切です。共感的に話を聞くことで安心感が生まれ、本人が症状を正直に伝えやすくなります。
また、日常の中で「どんな時に痛みが強いのか」「どのような食事や行動で悪化するのか」を聞き取ってあげると、医療機関に相談する際の大切な情報にもなります。
病院受診を勧める
夜の腹痛が毎日のように続く場合、放置するのは非常に危険です。胃潰瘍や過敏性腸症候群といった機能性疾患から、がんや婦人科系疾患など重大な病気まで幅広く考えられるため、早めの受診が欠かせません。
しかし、本人が「大したことはない」と思って受診を後回しにしてしまうケースも少なくありません。
家族や周囲が「気になるから一度診てもらおう」と優しく声をかけ、背中を押すことが大切です。
特に強い痛みが続く、血便や吐血が見られる、体重減少があるといった危険サインがある場合は、できるだけ早急に医療機関を受診するよう促しましょう。
食事や生活リズムを一緒に整える
腹痛の改善には、本人だけでなく家族全体で生活習慣を整えることが効果的です。例えば、就寝前の重たい食事を控えたり、アルコールや脂っこい料理を避けたりといった工夫は、家庭全体で取り組むことで負担が軽減されます。
また、食卓に消化に優しい料理や低FODMAP食品を取り入れるなど、本人が安心して食べられる環境を整えることも重要です。
加えて、規則正しい睡眠習慣を一緒に心がけることで、自律神経の安定にもつながります。生活リズムを家族で合わせることで本人が孤独感を抱かず、無理なく改善を継続できる点が大きなメリットです。
無理をさせないようサポートする
症状がある人に対して「我慢してでもやるべき」と無理をさせることは逆効果です。腹痛を抱えながらの仕事や家事は心身に大きな負担をかけ、悪循環を生む可能性があります。
家族や周囲ができることは、必要に応じて役割を代わってあげたり、休養を勧めたりして、安心して休める環境をつくることです。
また、精神的なプレッシャーが症状を悪化させることも多いため「できる範囲で大丈夫」という姿勢で支えることが大切です。
本人が安心して生活できる環境が整えば、症状の改善だけでなく治療への意欲も高まり、長期的な健康維持につながります。
まとめ

夜になると毎日続く腹痛は、生活習慣やストレスが関与するケースから、消化器疾患や婦人科系の病気、さらには重篤な疾患のサインである可能性まで多岐にわたります。
まずは症状を軽視せず、セルフチェックや生活改善を行いながら、必要に応じて内科や消化器内科、婦人科を受診することが重要です。
また、家族や周囲の理解と協力も大きな支えとなり、安心して治療や生活改善に取り組める環境が整います。日常の中でできることを積み重ねつつ、医師の指導を受けて適切に対処することで、腹痛の改善と再発予防が可能になります。
決して一人で抱え込まず、周囲と連携しながら取り組むことが健康回復への第一歩です。